飛山濃水が生む個性豊かな味わい!岐阜の酒蔵が醸す日本酒を紹介
日本のほぼ中心に位置する岐阜県は7つの県に囲まれ、全国で7番目に大きい面積を持つ内陸県だ。北部には飛騨山脈、乗鞍岳、御嶽山、奥穂高岳といった標高3,000m級の山々が連なり、南部には木曽三川が流れる自然に恵まれた環境を持つ。本記事ではSake World NFTで取り扱いがある岐阜県内の酒蔵とおすすめ銘柄を紹介すると同時に、岐阜の日本酒の特徴と歴史を振り返る。

岐阜県の酒造りは江戸時代中頃にまで遡り、県内にある半数以上の酒蔵は江戸時代の創業となる。地理的環境から越後杜氏の数が多く、次いで南部杜氏が続く。
大きな面積を持つ岐阜県は海抜0メートルの平野部から3,000メートルを超える山脈まで、標高差の大きい県である。古くから「飛騨の山、美濃の水」といった意味で「飛山濃水(ひさんのうすい)」と呼ばれ、地域によって気候も異なる。
山岳地帯に位置する北部では、夏は冷涼であり、冬季は積雪の多い地域。濃尾平野が広がる南部の美濃地域では、木曽川、長良川、揖斐川という「木曽三川」が流れ、名水と称される湧き水や河川に富んでいる。豊かな自然、水、そして土地を活かし、現在は50近い酒蔵が日本酒を醸す。
【あわせて読みたい】
・NFTとは?
・購入方法はこちらから!
・Sake World NFTはこちら
INDEX
清らかな水に恵まれた岐阜県の日本酒
北アルプス・白山・伊吹山・恵那山といった山々の雪解け水が流れる岐阜県には、長良川・飛騨川・木曽川・揖斐川といった大きな河川を有している。清らかな水が豊富に得られる環境は、日本酒造りにとって欠かせない要素の一つだ。
また、豊かな自然環境から米作りも盛んに行われている。岐阜県を代表する酒造好適米「ひだほまれ」は大粒であり、タンパク質が少なく、心白の発現率が高いという酒造りに適した特徴を持つ。
県内では酵母の開発にも積極的であり、1997年(平成9年)には県オリジナル酵母として「G酵母」を育種。2002年(平成14年)にはリンゴ酸を多く生成し、低アルコール清酒の製造を目的とした「多酸性G酵母」、2018年(平成30年)には優れた吟醸香を生み出す「G2酵母」を発表している。
幅広い地形と自然環境を有することから、岐阜県内でも地域ごとに個性豊かな日本酒が醸されている岐阜県。2026年には白川村と県内酒蔵が共同で新たな酒蔵を稼働させる予定となっており、多くのファンからの注目を集めている。
「Sake World NFT」で買える岐阜の日本酒
①「二木酒造」
1695(元禄8年)年創業。
二木酒造が創業した時代は飛騨の地が幕府直轄地となり、幕府から高山城破却の命令が出された頃に当たる。先代がもともと石川県に住んでいたことから、屋号は「加賀屋」で、酒蔵の入り口ののれんにもその名が染め抜かれている。
明治の初めの大火で蔵の大部分を消失したが、残っていた江戸時代の図面をもとに再建している。中央にある清冽な井戸は、過去の酒造りの仕込みに使っていたという。岐阜県産の普通米「あきたこまち」を60%精米して仕込む「玉の井」は、この井戸水にちなんで名付けられたものである。
『おススメの1本!』大吟醸 両面宿儺(りょうめんすくな)

両面宿儺とは、飛騨に現れたとされる偉業の人物を指す言葉。飛騨国から美濃国にかけての旧飛騨街道沿いには様々な伝承が残る。二つの顔は穏やかな表情の裏に、怒りを宿した顔をしており、四本の手足を持つ異形で表現される。
人気漫画「呪術廻戦」に同名のキャラクターが登場し、飛躍的に知名度を高めた伝説の存在を名に冠した一本は、大吟醸の豊かな香りと、まろやかでスッキリとしたお酒に仕上がっている。米の旨みが凝縮された香味が楽しめるだろう。
特定名称:大吟醸酒
原材料:米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール
使用米:一般米
アルコール度:15%
この記事の酒蔵はこちら

- 二木酒造
-
♯岐阜♯酒蔵
②「中島醸造」
1702年(元禄15年)創業。
岐阜・瑞浪の地で創業し、「始禄(しろく)」銘柄で長年地元で愛されてきたが、1900年代の終わりから、古酒造りやパウル・クレーの絵画をラベルに使用するなど、時代を先取りした取り組みを開始した。2000年には新銘柄「小左衛門」を立ち上げると同時に、酒米にも注力。地元産の酒米を育成するほか、選び抜いた多種類の酒造好適米を用いて、さまざまなタイプの酒を醸している。
様々な手法の日本酒作りを手掛けており、正統派から個性的なものまで幅広いバリエーションが中島醸造の大きな魅力である。2018年には新蔵を設置して四季造りへと移行。2024年春にオープンした「cafe shiroku」「ristorante solo」は、お酒を飲まない人でも愉しめる空間となっている。
『おススメの1本!』小左衛門 再仕込貴醸酒 白麹
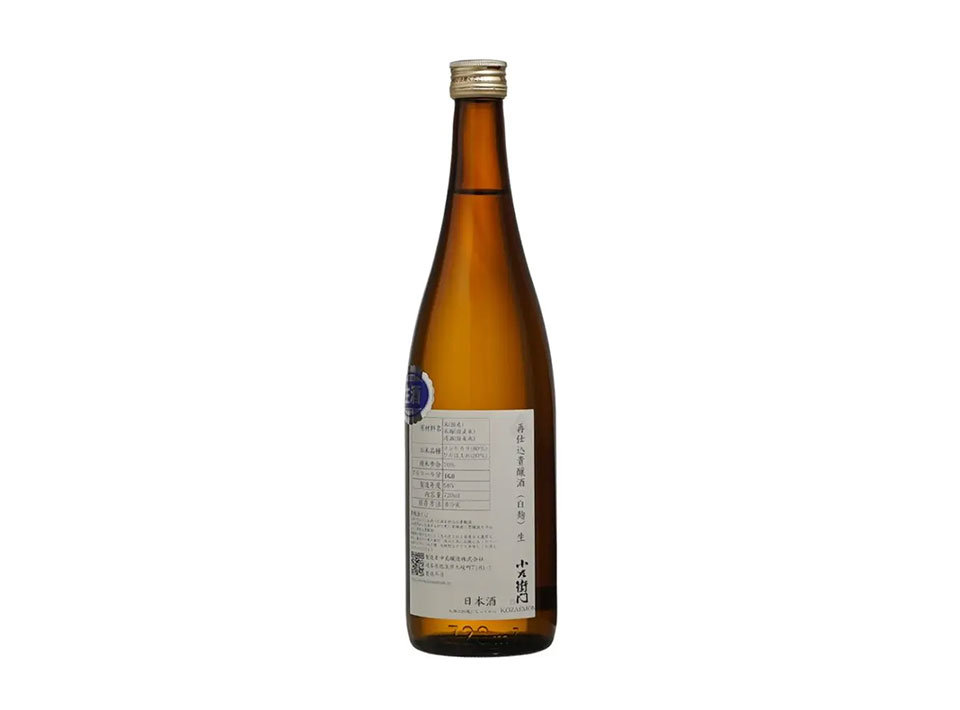
貴醸酒とは仕込みの最旬段階において、水の代わりに日本酒を使用することで生まれる極甘口の日本酒だ。
本品ではその造りにおいて、日本酒ではなく貴醸酒を使用することで、より贅沢な甘みが楽しめる。また、使用する白麹は通常焼酎造りに使用されるものであり、クエン酸を生成するという特徴を持つ。貴醸酒特有の甘みと白麹由来の酸味が同時に楽しめる貴重な一本だ。
特定名称:普通酒
原材料:米(国産)、米こうじ(国産米)
使用米:コシヒカリ80%、ひだほまれ20%
アルコール度:16%
この記事の酒蔵はこちら

- 中島醸造
-
岐阜♯酒蔵♯岐阜
③「玉泉堂酒造」
1806年(文化3年)創業。
標高859mの養老山地と豊かな水の恵みを受ける名瀑「養老の滝」がある養老の地に佇む[玉泉堂酒造]。「養老の滝」に加え「菊水泉」の湧水を源にもつ養老山系伏流水を使い、伝統と革新の酒造りを目指している。
1934年から進めてきたのは、歴史と伝統を守りながらも新たなチャレンジに挑む酒造り。日本酒だけでなく、焼酎、ウイスキー、リキュール、みりんに至るまでこだわりの酒造りを広げている。
垢抜けて品格ある酒を目指しており、機械化できる工程と手作業を駆使しながら、繊細で抜かりのない酒造りを行う。
『おススメの1本!』美濃菊 純米大吟醸中汲み原酒 冷蔵熟成三年
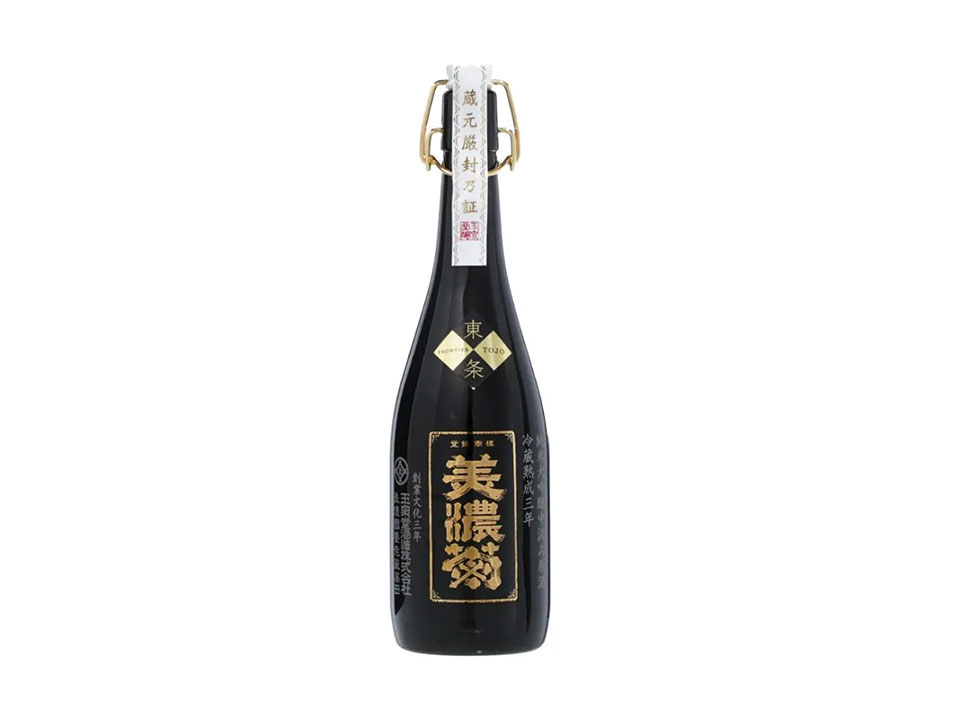
地元だけではなく、関東でも広く愛されている美濃菊銘柄。昔ながらの吟醸酵母、兵庫県特A地区東条産「山田錦」を全量使用し、厳冬に大吟醸専用蔵での小仕込みで丁寧に仕込まれる。
「造りの優れた日本酒は適度な熟成によって至高の旨味を得ることができる」という考えのもと、この銘柄は酒蔵の冷蔵庫の奥深くで三年以上の歳月を経て、ようやく出荷される。上品で優美な香り、柔らかく上質な米の旨味が感じられる至極の一本だ。
特定名称:純米大吟醸
原材料:米(国産)、米こうじ(国産米)
使用米:兵庫県東条産特A地区山田錦
アルコール度:16%
この記事の酒蔵はこちら

- 玉泉堂酒造
-
岐阜♯酒蔵♯岐阜
④「所酒造」
明治初頭創業。
[所酒造]は木曽水系に属する揖斐川の上流で、小規模ながら存在感のある酒蔵を目指し、丁寧な酒造りを手掛けてきた。食中酒をテーマに米の旨みと酸味をしっかりと感じられる酒を醸し、数年単位の熟成にも耐えうる旨みが強い純米酒を手掛ける。
生産する日本酒の9割を純米酒が占め、全体の半分以上は無濾過生原酒。純米大吟醸や無濾過生原酒となると、冷やして飲むことを勧められる場合が多いが、同蔵では気分や料理に合わせ、燗にするのも新たな発見ができる飲み方として推奨している。
『おススメの1本!』兎心(ところ)GOLD

全量山田錦を使用した純米大吟醸酒の中汲みをしぼった直後に瓶詰し、おりをからめて瓶内2次発酵を行うことで軽いガス感をもたせた微発砲清酒。やや甘めの味わいは食前、食後酒としての飲用やスイーツとの相性抜群。華やかな香りと旨味、酸味、ガス感が絶妙に調和する兎心シリーズ最高峰の1本だ。
特定名称:純米大吟醸
原材料:米(国産)、米こうじ(国産米)
使用米:山田錦
アルコール度:16%
この記事の酒蔵はこちら

- 所酒造
-
岐阜♯岐阜♯酒蔵
⑤「平瀬酒造店」
1623年(元和9年)創業。
城下町高山で400年、酒造りひと筋に生きる酒蔵であり、北アルプスの清らかな伏流水と飛騨の米、そして冬の厳しい寒さがこの土地ならではの酒を醸している。
代表銘柄の「久寿玉(くすだま)」は、おめでたい席に飾られる「薬玉」が語源とされており、地元で長く親しまれている。現在は15代目当主の平瀬市兵衛氏が400年の歴史を守る。「他の商売には、いかなることがあっても絶対に振り向かないこと。酒造り業ひと筋に生きる」という家訓からもうかがえる、実直なまでの酒造りの「心」を味わいたい。
『おススメの1本!』久寿玉 純米大吟醸生貯蔵酒400年記念

酒造好適米である岐阜県産ひだほまれを100%使用した純米大吟醸生貯蔵酒。華やかな吟醸香と、さわやかな酸味、フレッシュな味わいとまろやかな旨みの両方が楽しめる。[平瀬酒造店]創業400年を記念した、貴重な記念酒だ。
特定名称:純米大吟醸
原材料:米、米こうじ
使用米:ひだほまれ
アルコール度:16%
この記事の酒蔵はこちら

- 平瀬酒造店
-
岐阜♯酒蔵♯岐阜
多彩な魅力をもつ銘柄が揃う岐阜県
豊かな自然と清らかな水に恵まれた岐阜県は、江戸時代から酒造りが盛んな地域となっている。飛騨の山々や木曽三川の恵みを受け、約50の酒蔵がそれぞれの風土を活かした酒を醸している。
県オリジナル品種や「G酵母」の開発など、伝統を守りつつ酒質向上へ向けた取り組みにも積極的だ。
本記事では、Sake World NFTで取り扱われる岐阜の酒蔵を紹介した。歴史の中の伝説を冠した酒や、甘みと酸味が調和した個性派の一本、熟成させた上品な味わいの酒など、多彩な魅力を持つ銘柄が揃う。岐阜県ならではの酒文化をぜひ味わってほしい。
ライター:新井勇貴
滋賀県出身・京都市在住/酒匠・SAKE DIPLOMA・SAKE検定講師・ワインエキスパート
お酒好きが高じて大学卒業後は京都市内の酒屋へ就職。その後、食品メーカー営業を経てフリーライターに転身しました。専門ジャンルは伝統料理と酒。記事を通して日本酒の魅力を広められるように精進してまいります。








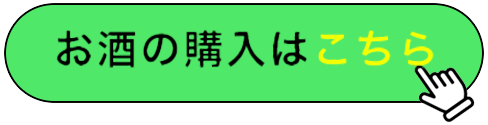









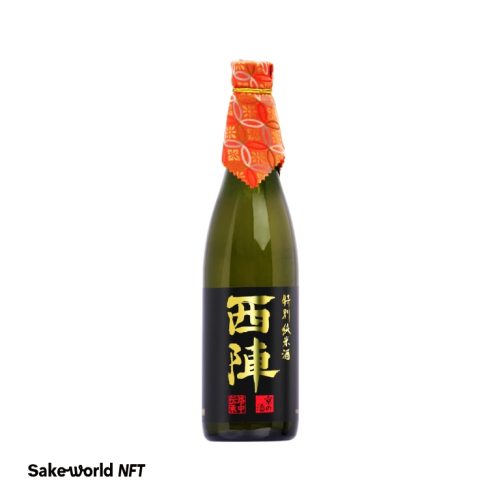




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















