株式会社Agnavi 代表 玄成秀さんが語る「ICHI-GO-CAN®」で目指す地域活性とは?
60銘柄の「ICHI-GO-CAN®」を取り揃えたイベント「NIPPON SAKE TRIP!!」が6月20日(木)から22日(土)の3日間、東京・新橋で開催された。「ICHI-GO-CAN®」を展開する株式会社Agnaviの代表取締役である玄成秀さんに日本酒への想いを聞いた。

全国各地の日本酒60銘柄を取り揃えたイベント「NIPPON SAKE TRIP!!」が6月20日(木)から22日(土)の3日間、東京・新橋の駅前にあるカフェ型スペース「カフェピアッザ」で行われた。株式会社Agnaviが展開する日本酒ブランド「ICHI-GO-CAN®」を中心とした日本酒を楽しめる本イベント。イベント初日に行われたメディア限定先行オープンを取材した。
INDEX
「ICHI-GO-CAN®」から60銘柄の日本酒が集結
「NIPPON SAKE TRIP!!」は地域活性化を目指す株式会社Agnaviと地域コミュニティの活性化を目指す「カフェピアッザ」を運営するPIAZZA株式会社の両社の協同で開催されたイベント。JR東日本グループでスタートアップ企業への出資や協業を推進するJR東日本スタートアップ株式会社の資本業務提携先である両社が、全国各地の酒蔵や食の魅力を発信し、観光流動を創出することを目的にこのたび開催に繋がった。

イベントでは「ICHI-GO-CAN®」の中から厳選した日本酒と、三陸産ホタテ五目釜メシや瀬戸内牛すじ煮込みなど、日本酒に合うその産地こだわりの食事を楽しむことができた。日本酒だけでなく、その日本酒の郷土料理を一緒に楽しむことでその土地への興味関心がより強まる仕掛けになっている。
この方に話を聞きました

- 株式会社Agnavi 代表取締役 玄成秀さん
-
プロフィール1992年生。2020年 株式会社Agnaviを創業し、代表取締役CEOを務める。
株式会社Agnaviの代表取締役である玄成秀さんは、「知らないけれども美味しいお酒はたくさんあります。今回のようなイベントで偶然の出会いやご縁から『このお酒美味しかった』、『これはどこのお酒だろう』と地域を知ってもらうきっかけ作りをこうした人が集まる場所でやれるのは嬉しいです。地域ごとに出身地やよさ、魅力があり、お酒も同じ。その違いを楽しんでもらい、お気に入りの1本を見つけもらえる取り組みができればと思っています」と本イベントへの想いを語っていた。
提携蔵元が100を超えた「ICHI-GO-CAN®」
3年前のコロナ禍にスタートした「ICHI-GO-CAN®」は、“適量・オシャレ・持ち運びベンリ・環境にも優しい”を実現させた1合180mLの日本酒ブランド。全国170種類以上の地酒を取りまとめて販売しており、提携蔵元は100を超える。

これまで日本酒は紙や瓶で流通していることが主流であり、缶の日本酒の流通はほとんどなかった。これは蔵元が缶でたくさんのロットを卸す難しさがあるため。そもそも蔵元は蔵自体が文化遺産登録されていることも多く、新たに缶に対応するための初期投資費用や設備が難しい現状がある。
こうしたなかで、同社は蔵元から日本酒をタンクで購入し、消費者の近くまで持ってきて集約化することで物流問題を解決。鮮度の高いものを急速殺菌で後から火入れし、その都度缶詰めして出荷することで蔵元の負担なく、缶で日本酒を提供することを可能にした。
日本酒業界全体をひとつの会社と見て儲かるように
日本酒の消費量は年々減少傾向にあり、数多くの酒蔵が売上に悩んでいる昨今。そもそも「ICHI-GO-CAN®」がスタートしたきっかけは、もともとコロナ禍が始まったばかりの頃に、全国の酒蔵を支援するプロジェクトを始めたところ、大きな成果が得られたとのこと。瓶だとおじさんのイメージが強く、なかなか若い世代に売れなかったビール市場が缶タイプを始めたことで売上が伸びたことから日本酒にも応用できると考えたそう。
「多くの蔵元様がいい酒を造ることはできても、ブランディングが不足してしまっています。これは昔ながらの職人気質も起因しているのでしょう。一方で消費者は美味しい酒があるのに知らないから飲めていない。消費者も蔵元様も機会損失をしているのはとてももったいない。既存の日本酒を飲んでいた層を大事にしつつも、まだまだ日本酒のよさを知らない若年層と海外のマーケットを捉えることでビジネスとしても差別化していこうと思って展開してきました」と玄さん。

「ICHI-GO-CAN®」として日本酒を販売するために必要な流通整備や戦略的売り方、そしてそれを実行するまでの社内体制。当初は「缶にするなんて」とネガティブな反応を持っていた蔵元も、実際に「ICHI-GO-CAN®」と提携したことで売上が伸びたことで喜ばれているという。
「自社が儲かることも大事ですが、蔵元様が儲からなければ意味がありません。日本酒業界をひとつの会社と捉えて、売上を伸ばしていくことが大事だと思っています」と玄さん。
酒蔵が儲かればその地域の農家や飲食店、宿泊施設も儲かる
今回のイベントは、地域活性というのも大きなキーワードだ。地域活性と言うとアニメや漫画など若年層に人気のコンテンツを使って地方を盛り上げるイメージがどうしても強いもの。日本酒自体がまだまだ若年層の人気を確立できていない中で、さらに地方活性となるとハードルが高いように感じてしまう。この点について玄さんは「地域活性ツールとしての日本酒はとても大きな力を持つ」と話す。

「そもそも日本酒を作ってきた蔵元様は、昔からその土地の地主であったり農家に田んぼを貸していたり商店を営めるようにしたりと、地域の主要な存在です。その酒が売れれば当然ながら農家も儲かり、その地域に人が来て商店で物を買って飲食を楽しみ、宿泊するようになる。蔵元様が儲かることで枝葉のようにその周辺が儲かっていく仕組みになる。こうした地域活性の流れは日本酒だからこそできることだと思っています」と玄さん。
日本酒の美味しさをより多くの人にマッチングさせる機会をいかに多く作るか。蔵元だけでなく、日本酒業界全体が儲かることで地域活性へと繋げていく同社は日本国内の若年層だけでなく、海外にも広く目を向けているそう。実際に現在では、北米や南米、東南アジア、ヨーロッパなど海外への輸出も積極的に行っている。

今回のイベントで筆者は初めて「ICHI-GO-CAN®」を飲んでみた。まず小さな缶がズラっと並んでいる中から産地や銘柄名など直感で選ぶ楽しさがイベント感満載。そして手に取りやすいサイズ感は見た目からしても可愛らしく、手に取って写真を撮るだけでもテンションが上がる。また180mlの分量はスっと飲み干せて、とても飲みやすかった。開封前であればバッグの中に入れても重たくなく、冷蔵庫に入れても場所を取らないなど、缶のよさを改めて感じることができた。

適量で持ち運びやすく、飲みやすい「ICHI-GO-CAN®」ブランド。日本酒初心者でも楽しみやすいブランディングや仕掛け作りによって、これからもさらに広がっていく予感がした。
ライター:エタノール純子
さまざまなお酒を飲み歩き、30歳を過ぎて日本酒に行きつく
最近はスパークリング日本酒にハマっている

















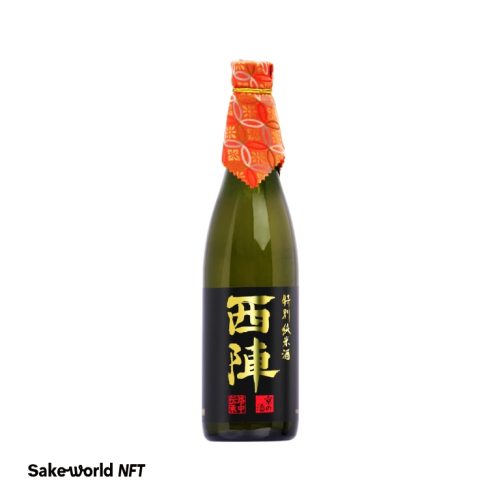




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















