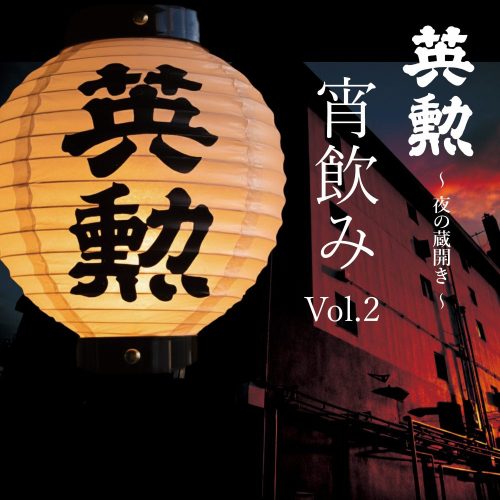【今さら聞けない教えて!?シリーズ16】滓引きと濾過~清らかに澄み渡れ!
酒は、滓引きと濾過によって、洗練と精製の洗礼を与えられ、透明なボディを手に入れます。 今回は、お酒が透明になるまでのお話です。

タンクの中から無防備な姿をさらしていた醪は、上槽によって原酒と酒粕に分けられたあと、滓引きされ、さらに濾過されます。今回は、滓引きと濾過ついてお話しします。
前回:【今さら聞けない教えて!?シリーズ15】上槽 ~ 袋吊りと自動圧搾機について
この方が解説します

- 杜氏屋主人・プロデューサー中野恵利さん
-
プロフィール1995年、大阪・天神橋筋に日本酒バー「Janapese Refined Sake Bar 杜氏屋」を開店。日本酒評論家、セミナー講師、作詞家としてさまざまな分野で活躍。
●滓の正体
搾りたての原酒には、酒袋の目から漏れ出た、分解されなかった米の欠片や酵母、麹菌が産出した酵素など、微細な固形分が混在しています。これが滓です。
滓には、デンプンやタンパク質、繊維質が含まれ、酵母や酵素が発酵を持続させるため、酒の香味は時を追って変化していきます。
●滓引き
この濁った原酒をタンクの中で数日置き、白濁した成分を全て沈殿させます。上層部が澄みきったところで、タンクの下部に二つある呑穴(抽出口)のうち、上側にある上呑から上澄み部分を抜くように汲み取ります。これが滓引きです。
上呑で汲みきれなかった底部分の酒も斗瓶に取り、数日後、滓部分と上澄み部分を取り分けます。
(滓も一緒に詰めたい場合は、下側の下呑と呼ばれる穴から抜き取ります。 “ おりがらみ ” と表記されているものがこれに当たります)
●坊主は縁の下の力持ち
酒蔵見学の際、醪が入ったタンクを覗き見ることはあっても、空っぽのタンクを覗き見ることは滅多にないと思われます。タンクの底は球状に盛り上がっていて、この部分は “ 坊主 ” と呼ばれています。坊主のお陰で、滓は盛り上がった球の周り、山下と呼ばれる部分に溜まるため、滓引きがしやすいのです。内容量が少なくなると、タンクの一方をジャッキアップして傾けますが、その際にも酒がタンクに残りにくくなります。また、櫂入れがしやすい、醪の対流を促すなど、坊主は縁の下の力持ちのように、タンクの下で酒造りを支えています。

●濾過
緑色を帯びて輝く、一見透明に見える滓引き後の酒ですが、微細な濁り成分が残存している可能性があるため、さらに濾過を行います。濾過は、香味の調和、劣化防止、酒質の安定、そして、酒を清澄にするために行われます。
●活性炭と珪藻土
炭素質の高い吸着性を利用して、活性炭で濾過を行うことは広く知られていることではないでしょうか。色素の吸着力が際立っていますが、色を吸着しやすいもの、香りを吸着しやすいもの、不要な味を吸着しやすいものなど、複数種類あり、目的によって使い分けたり、ブレンドしたりします。
この工程で、酒に炭素臭が付着することがあると言われますが、炭素の成分が酒に留まることはほとんどなく、そういった事案を濾過後の品質検査で見過ごすことはありません。
また、濾過助剤として濾過材の表面に珪藻土を付着し、珪藻土の多孔質を利用して濾過効率を向上させる方法もあります。この場合も、異なる役割を果たす珪藻土をブレンドして使用することがあります。
●膜という名のフィルター
メンブレンフィルターは細かなものを除去することに適しており、滓やゴミだけではなく、デンプン粒や酵母まで取り除くことが出来ます。膜を意味するメンブレン(Membrane)という言葉の通り、粒子や微生物を除去するためのフィルターは膜状になっています。
●これが主流? SFフィルター
微細な成分をとことん除去できるのがSFフィルター。これが現在主流だと思われる濾過の方法です。ハウジングと呼ばれる筒の中に、細さ0.4㎛以下の中空糸膜で出来たストロー状のフィルターが、束ねられた素麺のような状態で入っています。ストロー状のフィルターには微細な孔があり、外側から圧送された液体が孔を通ることで濾過される仕組みになっています。
濾材の臭いを移すことなく濾過でき、高温水洗浄を可能にしたことも主流となった要因ではないでしょうか。

●揺れる色
胡粉色でも卯の花の色でもなく、乳白色とも生成り色とも言い難い醪の色は、滓引きされ、濾過され、清澄な液体へと変容します。その揺蕩(たゆた)う色に心奪われることもまた、酒の愉しみなのです。
滓引きをしたあと濾過を行わず出荷するものには “ 無濾過 ” と表記されます。
前回:【今さら聞けない教えて!?シリーズ15】上槽 ~ 袋吊りと自動圧搾機について

























![店では出せないワクワクと楽しみがある場所My Sake World体験レビュー[Mr SAKE2024準グランプリ 島田昇忠さん]](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/noritada_shimada-500x500.jpg)
![[徳島/本家松浦酒造場]酒蔵を中心に地域活性化につなげる「酒蔵体験プログラム」を取材](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/main_narutotai-500x500.jpg)




![酒を起点に人が渦巻く街広島・竹原[前川酒店]と[道の駅たけはら]を探訪](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/11/1-600x337.jpg)