【豆知識】生酒・生詰め酒・生貯蔵酒の違いは「火入れ」。世界に誇れる技術、日本酒の火入れについて知りたい!
火入れとは、日本酒の品質を安定させるために低温で殺菌すること。実は世界に先駆けて開発されたすごい技術だったんです。気になる「火入れ」について唎酒師の藤田えり子さんが解説します。

生酒・生詰め酒・生貯蔵酒はどう違う?
よく似た言葉ですが、生酒と生詰め酒、生貯蔵酒の違い、わかりますか? ちょっと意外に思われるかもしれませんが、実は生詰めと生貯蔵酒は「生」ではありません。生酒とは火入れをしていない日本酒のこと。生詰めと生貯蔵酒はそれぞれ1回きりですが、火入れ(加熱殺菌処理)をしたお酒ということになります。
一般に日本酒は貯蔵前と瓶詰め時の2回に分けて火入れをしますが、生詰めは貯蔵前、生貯蔵酒は瓶詰めの時だけ行っています。生詰め酒はフレッシュな感じが残り、生貯蔵酒はおだやかな味わい。いずれも火入れをしているので、生酒よりは品質が変化しにくいといえます。
ちなみに生詰め酒の代表格が、秋を待って出荷される「ひやおろし」。夏を越して落ち着いた味わいとやや残るフレッシュさが相まった、この時期にしか楽しめない特別なお酒です。

火入れの方法もさまざま
火入れには腐敗の原因になる火落ち菌(乳酸菌の一種)を殺菌し、味を劣化させる酵素の働きをストップさせて、保存をしやすくする目的があります。
お酒の温度が約60〜65℃になるように加熱してから急冷しますが、それにはいくつかの方法があります。昔よく行われていたのが熱湯に浸けた蛇管という螺旋状の細い管にお酒を通す方法ですが、現在ではプレートヒーターを使用したり、瓶詰めしたお酒に熱湯のシャワーをかける方法が主流になっています。特に吟醸酒などは瓶に詰めて湯煎する瓶燗火入れを行い、繊細な風味を損なわないよう工夫されています。
さらに技術革新も進んでおり、電気による瞬間加熱法によって、まるで生酒のような風味を保ったまま、安定性を高められる最新機器を導入している酒蔵も大手を中心に増えています。

パスツールより300年早かったスゴ技
ところで加熱をして殺菌する火入れの技術は、いつから始まったのでしょうか。奈良の興福寺の塔頭である多聞院の僧が残した文献『多聞院日記』によると、永禄11(1568)年に日本酒の火入れについての記述が見られ、すでに室町時代末期には行われていたことになります。顕微鏡の発明によって微生物が発見されたのが1680年頃、さらにフランスの科学者パスツールが低温加熱によるワインの殺菌法を発表したのが1865年です。なんと300年以上も時代を遡って、今に通じる加熱殺菌の技術が開発されていたのですね。
生酒のフレッシュさもいいけれど、火入れしたお酒の落ち着いた味わいは料理を引き立てて食中酒にぴったりです。世界に先駆けて技術を開発した先人に敬意を表して、火入れの日本酒のおいしさを見直してみてはいかがでしょうか。
ライター・唎酒師 藤田えり子
大阪の日本酒専門店に世界を広げていただき、さまざまな日本酒や酒蔵に出合う。好きな日本酒は秋鹿、王祿ほか
お酒以外の趣味は鉱物集めとアゲハ蝶飼育。


















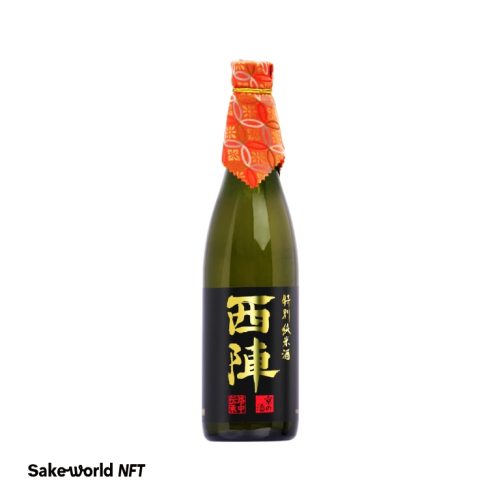




![[WORLD KYOTO]×[Sake World]肩を並べて飲む! 日本酒と音楽の楽しき世界](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/top-500x500.jpg)
![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)



















