【豆知識】泡立つ日本酒はなぜ?日本酒のもろみについて知りたい!
酒蔵見学で仕込みタンクをのぞかせてもらうと、発酵中のお酒のもとは元気よく泡立っています。この泡の正体はなんでしょう? 気になる「泡」について唎酒師の藤田えり子さんが解説します。

日本酒の泡はアルコール発酵由来
爽やかな飲み口のスパークリング日本酒の魅力はシュワっと立ち上る泡。また、生酒にも微発泡のものがありますね。これらの泡はいずれも自然由来のものですが、いったいどこから生まれてくるのでしょうか。
それについては、まずアルコール発酵の仕組みをおさらいしておきましょう。
アルコール発酵とは酵母が糖を分解して、アルコールと炭酸ガス(二酸化炭素)を作り出す反応のこと。日本酒のもとがアルコールを作るのは「もろみ」の段階で、仕込みタンクの中では米麹が作る糖と酵母が出合って発酵が進み、ぷくぷくと炭酸ガスの泡を立てています。この炭酸ガスは通常、火入れなどの工程で消えてしまいますが、そのまま残して瓶に閉じ込めたものがスパークリング日本酒といわれるものです(後から炭酸ガスを添加する銘柄もあります)。

泡は厄介だけど、大切な役割も
このもろみの泡ですが、お酒を造る蔵人にとっては困った存在。仕込みタンクには炭酸ガス、つまり二酸化炭素が充満した状態で、うっかり中に落ちてしまうと窒息して命に関わる大事故になってしまいます。また、酒蔵見学などでもろみの香りを嗅ごうとしてタンクに顔を突っ込みすぎ、鼻がツンとなった経験のある人はいませんか。これは鼻の奥で炭酸ガスが水分と反応して炭酸となり、弱酸性の刺激を感じるからなのだとか。
特にもろみの発酵のピーク時には、盛り上がるような泡(高泡)が大量に出るので、タンクからあふれてしまわないように泡消し機を回転させて抑え込みます。昔は人の手で寝ずの番をしていたそうで、いろいろな苦労がありました。この泡が消えにくいのは、気泡の周りを覆うように酵母が付着しているため。なので、泡と一緒にせっかくの酵母もあふれて減ってしまうと、発酵力が弱くなるので注意をする必要があります。
その一方で、もろみの泡は発酵の目印となる大切な役割も果たしています。しっかりと立った泡は、酵母が元気に働いている証拠。日ごとに変化する泡の様子を観察することで、発酵の進み具合がわかるのです。

今では泡なし酵母がほとんど
現在はほとんどの酒蔵が「泡なし酵母」を使用しています。これは発酵の際に高泡を作らないもので、1963年に酵母の突然変異が見つかり、研究を重ねた末、数年後「きょうかい701号」が初めて分離されました。実は一番最初の発見は大正5(1916)年のことだそうですが、当時は蔵の酒造りの規模が小さく、人手も充分にあったため、注目されないまま消えてしまったようです。
ちなみにきょうかい酵母名の末尾に「01」が付くのが泡なし酵母のしるしで、「きょうかい701号」はきょうかい7号の泡なし酵母ということになります。なお、泡なし酵母の場合、発酵の進み具合は成分分析をして判断します。
便利な泡なし酵母の誕生によって、蔵人の方の仕事が少し楽になりました。お酒を消費する立場の私たちには直接の関係はないものの、喜ばしいことですね。
ライター・唎酒師 藤田えり子
大阪の日本酒専門店に世界を広げていただき、さまざまな日本酒や酒蔵に出合う。好きな日本酒は秋鹿、王祿ほか
お酒以外の趣味は鉱物集めとアゲハ蝶飼育。


















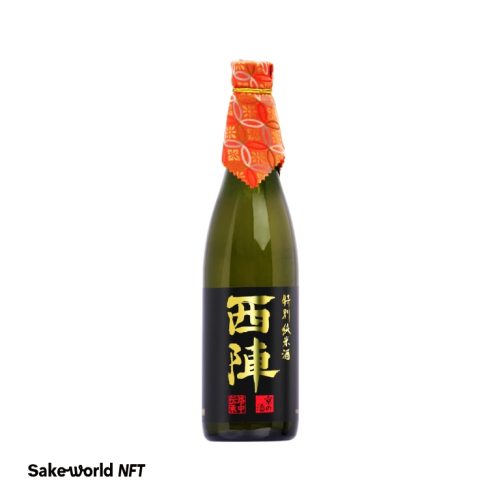




![[WORLD KYOTO]×[Sake World]肩を並べて飲む! 日本酒と音楽の楽しき世界](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/top-500x500.jpg)
![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)



















