日本酒の価値は「ストーリー」で伝える 大分・泰侍インタビュー(後編)
九州・大分を拠点に、国産の酒類を世界へ輸出するサポートに加えて、SAKEが持つ文化的価値を併せて伝えている泰侍株式会社。日本酒を含めた「國酒」を世界各国に紹介する中で、"外”だけでなく、”中”からも国際的な感覚を持ち合わせるための取り組みをしている。同じ九州人である旅するソムリエ・岸原文顕氏で実施したインタビューの後編では、同社が重視する「ストーリーテリング」を中心に、様々な角度から語る。

前編はこちらから
関連記事はこちら
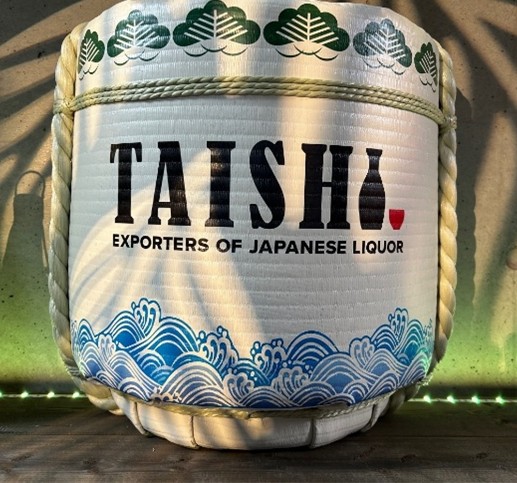
- 日本の未来を照らすものが『國酒』大分・泰侍インタビュー(前編)
-
♯大分
映像で伝える日本酒の価値
岸原:
「ストーリーテリング」についてもう少し具体的に教えてください。
幸松:
実際に酒造りの現場を見せていただき、造り手の話から感動することや驚くことが多くあり、次第にそれを周囲に伝えるようになりました。
「このお酒は、ここが本当にすごい」と話しているうちに、ノリさん(伊藤)と二人で一緒に語り合いながら発信するというアイデアが生まれました。
伊藤:
現在、香乙里さん(幸松)と一緒に取り組んでいることのひとつが、公式YouTubeチャンネル「Sip of Japan」の運営です。英語でも発信して、海外の方にも伝わるように工夫しています。英語学習のきっかけとして視聴してもらうことも意識していて、字幕も日本語と英語の両方を用意しております。日本酒や焼酎に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
Sip of Japanでは、お酒というものの背後にある「ストーリー」を伝えることを重視しています。
海外でお酒を販売するには教育が必要です。知られていなければ、そもそも売れませんから。
例えば北米の主要都市では、ある程度の認知度がありますが、少し地方に行くと「酒=酔っぱらうためのもの」というイメージがまだ強く、安価な酒という印象を持たれがちです。
そうしたイメージを持つ人に対して、例えば60ドル、70ドル、あるいは100ドルのボトルを売るためには、そもそもお酒とはどういうものかを理解してもらうことが大切です。
海外のレストランでは日本酒は相対的に高いのですが、それでもお金を払って飲んでくれるのは、良い体験ができるからです。Sip of Japanでは、教育的なコンテンツをどんどん発信したいと考えています。
岸原:
なぜ映像メディアなのでしょうか?
伊藤:
例えば今、井上酒造さんのドキュメンタリー映画を制作しています。
井上酒造さんには素晴らしいストーリーがあり、蔵としての魅力も十分にあります。さらに、社長の井上百合さんが中心となって酒造りを行っている点も特徴的です。酒米「雄町」の発芽をさせ田植えし、田んぼに仕込み水を流すほどこだわりが詰まっています。
撮影は今春から開始しており、来年の夏頃に公開を予定しています。一本の映画として制作するのは今回が初めてですが、きっと喜んでいただける内容になると思います。

井上酒造「百合仕込み」純米大吟醸 無濾過生原酒 中汲み
「Sip of Japan」でも、そうした造り手の思いを映像として残したいです。
他の蔵元の方々にも同様の思いがあります。お酒は年に一度しか造れないため、人生の中で残された回数は限られています。あと30回、あるいは10回しか造れないという方もいるかもしれません。その時々の造り手がどんな思いで、どんな情熱を持って酒を造っていたのかを記録として残すには、YouTubeは非常に有効な媒体です。
また資産にもなります。検索エンジンに引っかかるため、10年前の動画でも世界中からアクセスされる可能性があります。お酒に興味を持った人が英語や日本語で検索すれば、その動画が表示され、造り手のこだわりが伝わるのです。
岸原:
その情報を得た上で飲むと、より美味しく感じられるでしょう。教育を通じて、味わいが深まるということです。飲みながら映像を見ると、体験がさらに豊かになりますね。
伊藤:
どんな場所で、どんな人たちが造っているのかを視覚的に知ることは非常に価値があります。
映像では味や匂いは伝えられませんが、味や香りを想像させることは可能です。視覚的な情報や音を通じて、10分間で多くのことを伝えることができます。
将来的には、10年後、20年後にその映像が資料として活用されるかもしれません。その時に、「昔はこんな苦労をして造っていたんだ」と知ることができれば、嬉しく感じるでしょう。
蔵元が代替わりした際にも、前の造り手がどんな思いで酒を造っていたのかを知ることができるのは、非常に意義のあることです。関わる人が変わっても、蔵の歴史は積み重なっていきます。
「日本酒アッサンブラージュ」は、新たな日本酒文化

お二人が京都で実際にブレンドした酒。左が幸松さん、右が伊藤さん。共に「完璧なブレンド!」と振り返る。
岸原:
最近、京都に行かれた際にMy Sake Worldの「アッサンブラージュ」を試されたそうですね。
伊藤:
実際につくって飲んでみると、とても美味しく感じました。一本ずつ丁寧に造られていて、「ここが少し甘すぎる」「ここは少し苦い」といった部分をうまく補完し、全体としてバランスの取れた味わいに仕上がっていました。
幸松:
苦味や甘味のバランスを整えることで、飲みやすくなっていて、非常に繊細な仕上がりでした。
もともと私は、日本酒をカクテルに使うことに少し抵抗がありました。オレンジジュースなどを混ぜることに疑問を感じていたのです。売れるのであれば仕方ないとも思いますが、「本当にそれでいいのか」と罪悪感のようなものもありました。
しかし、「アッサンブラージュ」は本当の“ブレンド”だと感じました。
繊細な酒同士を素材として組み合わせることで、まるでクリスタルボールのような日本酒が生まれるのです。美味しかったので、ずっと飲み続けたいと思いました。
一つの蔵の酒だけでなく、他の蔵の酒や熟成酒も混ぜているため、味の幅が広がり、非常に面白い取り組みだと感じました。異なる要素を混ぜることで、個々の良さが際立つのです。
岸原:
先日、東京で外国人が多く集まるイベントで、このブレンド酒の展示試飲がありました。
フランス人の方が「これは何だ?」と聞くので、「アッサンブラージュだ」と伝えると「なるほど」と納得していました。ワイン文化の要素がベースにあるため、理解しやすかったようです。
一方で日本酒をブレンドするというのは新しい試みであり、蔵元のプライドもあるため、共通理解のもとで「良いものになる」という認識が必要そうですね。

東京で開催した「Blendtokyo」の様子。
伊藤:
My Sake Worldでのブレンド体験では、自分の好みに合わせてブレンドした酒を持ち帰り、テイスティングしながら「ブレンドとは何か」を考えるといった内容にしたいと思っています。

My Sake World体験時
※動画を見れない場合は、こちらのリンクからご確認ください。
各国のニーズを柔軟に対応したい
岸原:
輸出事業で、今後特に注力している市場はありますか?
幸松:
特定の国に注力するのではなく、各国のバイヤーのニーズに応じて柔軟に対応していて、これまでの10年間の活動を通じて世界中に日本酒が広まりつつあることを実感しています。
海外の輸入業者がどの酒を選べばよいか迷ったときには、地域や規模に応じて提案を行います。
冷蔵環境や製造方法によっても変わるため、まずは品質が劣化しにくいしっかりした造りの酒を勧めることが多いです。優れたバイヤーの目は肥えていて、瓶の形状、ラベルやキャップのデザインの細かい部分までしっかり評価します。
最近では、インドやインドネシアなど、これまで宗教的な理由で難しかった地域からも相談が寄せられるようになりました。これは新興国の可能性を感じさせる動きです。
伊藤:
私自身が住んでいたカナダや、家族と過ごしたことがあるフランスの地方部では、日本酒を見かけることはほとんどありませんでした。料理に使いたくても、安価なものすら手に入らない状況です。
そう考えると、まだまだ日本酒の流通は不十分だと感じます。
日本の田舎のスーパーには必ずビールがありますが、海外の田舎のスーパーで日本酒が1種類でも置かれていることは稀です。この現状を変えるためには、「國酒」としての価値を広められる志のある『仲間』となるような人材が必要です。
意識改革が必要な“母国”
岸原:
「仲間」という言葉が出ましたが、どういう人たちをイメージしますか?
伊藤:
日本でいえば、酒に対する価値を理解し、伝える力を持った若者です。
カナダでは、若い世代でも良いものにはお金を払って楽しむ文化がありますが、日本ではその意識が少し弱いと感じています。
安価な発泡酒やチューハイだけで満足するのではなく、國酒としてのアイデンティティや文化を感じながら飲む人が増えてほしいと思います。業界側で価格を上げることも重要ですが、それ以上に価値を理解する消費者が増えることが大切です。
幸松:
現在の海外での主な消費者イメージは、例えるならば、フィンテック業界で活躍する30代の男性です。
彼らは好奇心旺盛で冒険心があり、さまざまなものに対する嗜みのレベルが高く、アルコールにも深い知識を持っています。
ワインや牡蠣の味を知り尽くした人が、日本酒の熟成酒を飲んだときに、私たちも驚くような表現をしてくれることがあります。そうした評価のされ方に実際に触れると、日本酒の可能性を改めて感じます。
伊藤:
日本の若者の中では、ストロングゼロのチューハイとコンビニのおにぎりで満足するような生活も浸透しつつあり、文化的な価値が見過ごされているように感じます。
幸松:
戦前の日本には、工芸や文化の高度な技術がありましたが、現在はその息吹が失われつつあります。
また海外では、初めて焼酎を飲んだ人がその良さを深く語る姿を見かけますが、仮に今の日本人が初めてワインを飲んだときに同じように語れるかというと、難しいかもしれません。
日本に来る海外の友人を連れて食事に行くと、彼らは居酒屋だけでなく、ミシュラン級の寿司店にも足を運びます。しかし、日本人の若者は経済的な理由もあり、難しいのが現状です。食事を楽しみながら、酒を語るような人がどれだけいるのか疑問です。
良い酒を造っても、それを評価し、伝える若者がいなければ、価値は広まりません。作り手と飲み手の両方がパワフルであることが、文化の発展には不可欠です。
蔵元とバイヤーが同じエネルギーを持って向き合ったとき、商品は自然と流通します。どちらかが弱ければ流れは止まってしまい、綱引きのような緊張関係でいいものが生まれるのです。
それと同じで日本の若者がより豊かな暮らしを送り、文化に目を向けるようになれば、酒の価値も自然と高まります。ふるさと納税でようやく手に入れるというようなことではなく、適正価格で良い酒を楽しめる社会が理想です。
伊藤:
コロナ禍以降、宅飲みの文化が広まりました。飲食店で飲むよりも経済的なのだからこそ、安価なお酒ではなく、より上質な良いものを選んで飲んでほしいですね。
海外の30代の人々は、酒好きではなくても、知識を得ようとする姿勢があります。日本では、純米酒と本醸造の違いすら知らない人も多く、少し寂しさを感じます。
フランスでは、小学校で味見を通じてワイン文化を学びます。日本でも、國酒としての教育が必要だと感じています。海外のバイヤーからも、ファーストコンタクトの重要性が指摘されています。
香りや味を少しでも体験することで、酒の価値が伝わります。フランスでは家族で集まり、数時間かけて食事を楽しみ、異なるボトルを味わう文化があります。
子どもたちも会話を聞きながら、自然と知識を身につけていきます。
日本では、SNSなどで酒のデメリットばかりが強調されがちですが、酒には文化的な価値があることをもっと伝えていくべきです。外食文化の違いもありますが、友人の家でホストが酒を振る舞い、その酒について語るような文化が日本にも根付いてほしいと思います。
そのような会話がテーブルを豊かにし、酒の知識を広めるきっかけになります。フランスでは、子どもたちの前でワインについて家族が語り合う場面があり、それが文化の継承につながっています。
日本でも、そのように家族や友人との食卓酒を通じて文化を語り、伝える人が増えてほしいと願っています。
世界水準への対応力
岸原:
他に日本酒が直面している課題は何でしょうか?
幸松:
現在、「アルコールは健康に悪い」という認識が、世界的に広がっています。少量でも飲めば健康に影響があるという考え方が浸透しつつあります。
しかし、日本人にとってお酒は、神社とセットで考えられてきた文化的な存在です。神聖なものとして扱われ、長い歴史の中で大切に造られてきました。そうした精神性が、今も酒造りに深く根付いています。神様に捧げるお米の尊さを理解し、酒造りに込められた思いを知ることで、日本酒の価値がより深く伝わると感じています。
私自身も、お酒について何も知らず、お正月に少し飲む程度でしたが、日本酒の背景を知ることでその尊さに気づかされました。
海外の消費者も、日本酒の表面的な価値は感じているとは思いますが、それが神様と一体になるような気持ちで造られているということは、まだ十分に伝わっていないと感じています。
以前、免税品の仕事を依頼され、海外出張の際に免税店をよく訪れていたのですが、中国のお酒が80万円、100万円といった価格で並んでいるのを見て驚きました。カナダでは富裕層の華僑も多く、奥まった部屋では1500万円相当のウイスキーがディスプレーされたりと、売り場がまるで「お酒のオリンピック」のようだと感じました。
その一方で、日本酒は店舗の入口付近に冷蔵もされず、簡易的に並べられていることが多く、明らかに高級品としては評価されていないと感じました。
ある海外のバイヤーが蔵元に対し、「5万円以上のお酒を造れますか?」と聞いてきたことがあります。
しかしそのようなニーズはあっても、急に価格を上げることは難しいのが日本酒の現実で、価格については、今後の業界の運命を左右する重要なテーマだと思います。
中味だけではなく、デザインまで含めて価格に見合った価値の伝え方を工夫しなければ、蔵元が生き残っていくことは難しいでしょう。
岸原:
どのように価値を伝えればよいでしょうか?
幸松:
ワインやウイスキーの世界では、メーカーから独立したボトラーズが登場し、価値を高める取り組みが行われています。同じように、日本酒も複雑で貴重な「醸造酒」として発信していく必要があります。
例えば「1つのタンクからお酒が○○本しかつくれない」となると、「高級酒」として国内では高価だと感じられがちですが、海外ではそこからさらに6倍の価格がつくこともあります。
本来であれば、日本酒は国内でも1万円以上で販売しても良い品質があります。なのに、的確な情報が伝わっていないために価値が十分に認識されていないのです。
蔵元が100年、200年と存続するためには、1本あたりの価格設定を見直す必要があります。本来お酒は「もっと高価で貴重なもの」だという認識を広めるべきです。「なぜこんなに美味しいものがこの価格なのか」と疑問に思うこともあります。
岸原:
なぜ是正されないのでしょうか?
幸松:
日本酒の場合、出荷価格は卸価格から酒税を除いた金額で非常に安く見られてしまっており、それが過去10〜20年で定着してしまいました。出荷価格が1000円未満の銘柄もあり、すぐに価格を上げるのは難しい状況です。
海外に出す際には、法定表示のためのラベル貼りやプロモーション費用が発生します。それらを負担しなければならないことを考慮して出荷価格を見直すべきです。さらにPL保険や商標取得費用なども加味して、適正な価格設定が必要ですね。
仮に“裸”の価格のままで海外に出てしまうと、追加での費用負担を求められても対応できないことがあります。日本酒は他の酒類と違って表示上の課題もあるため、ラベルやパッケージにも工夫が求められます。
現状では、出荷段階ですでに赤字で販売している蔵元も多く、海外のバイヤーや小売店から、「ポスターをくれ」「プロモーションをしてくれ」と言われても対応できないのが実情です。
このような状況では、日本酒の浸透が止まってしまう原因にもなりかねません。テキーラのように、マージンをしっかり確保し販促物が充実している酒類と比べると、日本酒の蔵元は、販促支援の代わりに低い価格を維持せざるを得ず心情的にも上げづらい状況です。
しかし、米の価格も上がっており、このままでは次世代の蔵元の数が半分に減る可能性もあると聞いています。これは非常に深刻な問題です。
母国市場の日本人消費者の可処分所得が増えない状況で、価格設定にはジレンマがあります。長らく日本人だけに向けて造られてきた日本酒が、海外に出た途端に高額になってしまうということへの葛藤があります。
量が売れる日本酒は安価で販売されていますが、そうしたメーカーの価格設定を見てみると、非常に安価であることが分かります。
岸原:
輸出ロットについて、ウェブサイトを拝見すると「1箱から請け負います」と記載されていますね。横浜や神戸で集荷して、コンテナ単位でなくても、LCL(少量貨物)で対応してくれるという柔軟な姿勢が印象的です。
幸松:
「うちはそんなに出せないから」と遠慮する必要はなく、ワンパレットから始めたお客様が、やがてコンテナ単位に成長していくという流れが自然です。いきなりコンテナ単位で始めるのは難しいですが、少量から始めることで可能性が広がります。
岸原:
供給能力の問題はどうでしょうか?
幸松:
少量生産蔵の場合、良いバイヤーや市場があっても、供給が追いつかないという現実があります。
アメリカのスーパーマーケットは、欠品を非常に嫌います。常に在庫があることが求められるため、蔵元が未納税の酒を仕入れてボトリングし、安定的に供給できる体制がづくりなども必要です。
岸原:
いきなり設備投資するのはリスクがあり、製造量を増やせないというジレンマがあるとすれば、酒蔵同士で連合体のような形である程度の規模を作り、お互いのブランドを尊重しつつ協働することで、価格を上げつつ供給量も確保できるのでは。そうした意味ではSake Worldの「Assemblage Club」のような取り組みも有効でしょうね。貴重なお話をありがとうございました。

________________________________________
日本各地には、海外輸出をすでに長く続けている蔵元もいれば、始めたばかりの蔵元もあり、共通の悩みは販売数量をもっと伸ばしたいがそれは簡単ではないこと。
泰侍はその悩みに寄り添い、「蔵元のリスクも負う覚悟!」との幸松社長の言葉が印象的だった。3時間半におよんだ熱に満ちたインタビューを経て、筆者も「旅するソムリエ」として日本の誇るべき酒文化を世界に拡げていくという自身の志を新たにした。
ライター:
岸原文顕/ ソムリエ、HBAカクテルアドバイザー。日本酒をはじめ世界の酒類文化をこよなく愛する。世界3大ビールブランドや洋酒類のブランドマネジャーを歴任、
京都のクラフト醸造所経営など、国内外での酒類事業経験32年。日本発の志ある酒類の世界展開を支援。BOONE合同会社代表。全国通訳案内士。東京在住。
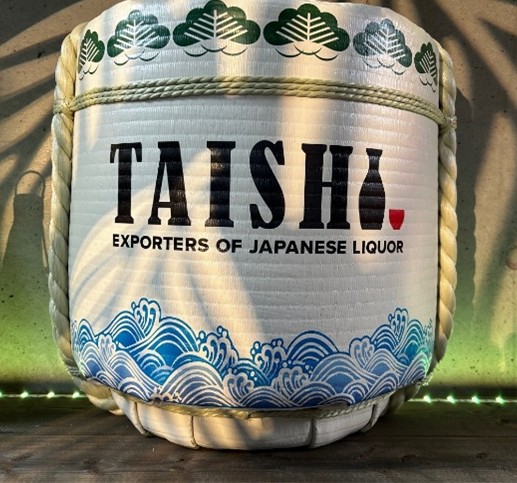

















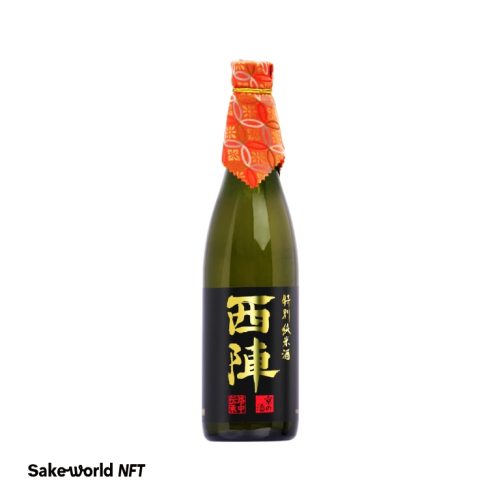




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















