創業160年の老舗酒蔵「龍勢」広島・藤井酒造
6代目蔵元が挑む酒造り革新
創業1863年、広島県竹原市の老舗酒蔵・藤井酒造。代表銘柄「龍勢」で知られる同蔵は、2021年に業界でも稀な「全量生酛仕込み」へと転換した。さらに酵母無添加という挑戦的な製法で、蔵付き酵母による日本酒造りを実践している。6代目蔵元・藤井義大氏が語る、伝統的製法への回帰と、そこに込められた日本文化継承の想いを探る。

INDEX
 海外から見出した「使命」
海外から見出した「使命」
「僕、地元が大嫌いだったんです」
開口一番、藤井酒造6代目当主・藤井義大(のりひろ)氏が口にしたのは意外な“告白”。
広島県竹原市の伝統的建造物保存地区に位置する老舗酒蔵の跡取りでありながら、幼少期から地元に馴染めなかったという。
竹原は、かつては塩業で栄えた裕福な町だったが、3歳まで東京で育ち、中学からは広島市内の学校、そして思春期を迎えた藤井少年には、その魅力は届いていなかった。
「地元に誇れるものなんて何もないように感じていました。ただただ、この町から出ていきたいと思っていましたね」
当時を振り返る藤井少年の転機となったのは、高校1年時のシンガポール留学だ。
「最初はカルチャーショックでした。『パクチーなんてカメムシの味やん※』と思いました(笑)」
※パクチーとカメムシはともにアルデヒドを成分に持つ
しかしこの異文化体験は、藤井少年の興味の対象が「世界」へと変わっていく。
その後、アメリカ・カリフォルニア州の大学で金融を学んだ藤井さんが目の当たりにしたのは、自国の文化を誇らしげに語る各国の学生たちの姿。
「日本人留学生って、文化の話になるとみんな途端に口をつぐんでしまうんです」
その違和感が、いつしか悔しさに変わった。
なぜ日本人は自分たちの文化をもっと誇れないのか――そこで思い起こしたのが、自らが生まれた造り酒屋の持つ文化と伝統だった。
「自分は日本の文化を伝える側の人間になろう。1人でも多くの人に『日本っていい国だな』と思ってもらえるような日本酒を造ろう」
その思いが、彼をふたたび竹原へと導く。
帰国後、東京で営業支援や広告事業に関わる会社に勤めた藤井氏だが、「30歳になったら竹原に帰る」ことを心に決めていた。
そして2013年、藤井氏は竹原に戻り、家業である藤井酒造に足を踏み入れる。
 龍勢、隆盛と再起
龍勢、隆盛と再起
藤井酒造の代表銘柄「龍勢(りゅうせい)」は、1863年の創業時から続く由緒あるブランドだ。1907年には日本初の全国清酒品評会で最優秀第一位を受賞し、日本一の栄誉に輝いた実績を持つ。
しかし戦後、品質維持が困難になり、「こんな酒を『龍勢』とは名乗れない」と、蔵ではいったんその名を封印する。
復活は1989年。5代目・義文氏の代に再興され、全国新酒鑑評会やIWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)など、国内外の評価を重ねた。
しかし。
華々しい実績の裏側で、藤井氏はある種の危機感を感じていた。
「スペックや等級、ラベルの外見に頼った酒造りでは、やがて限界が来る。味わいの一貫性や、酒造りの軸が見えづらくなっていたんです」
2013年に蔵に戻った藤井氏は、まず1年をかけて現場を観察。最初の仕事は、生酛の熟成酒[別格品]のリブランディングだった。
「この時造っていた雄町の生酛がとても印象的だったんです。これは、いま蔵が持っている個性を、もっと深く表現できるスタイルだと直感しました」
これを契機に、2017年には限定流通商品を全面的に刷新。同時に生酛の比率も段階的に引き上げ、蔵の方向性を定めていった。
 全量生酛仕込みへ――水害とコロナ禍の逆境で下した決断
全量生酛仕込みへ――水害とコロナ禍の逆境で下した決断
藤井酒造が“全量生酛仕込み”へと舵を切ったのは、2021年。その背景にあったのは、藤井氏の根源的な問いだった。
「なぜこの蔵で酒を造るのか、この蔵にしかできない酒造りとは何か」
生酛造りとは、蔵に棲みつく自然の乳酸菌を用いて酒母を育てる伝統的製法。現代の主流である速醸酛と比べ、仕込みには倍の時間がかかり、人手も必要だ。
しかし藤井氏は、その”非効率”にこそ価値があると信じた。
「自然の力を信じて、手をかける。そうやって生まれる酒は、“造る”というより、“授かる”ものだと思うようになりました」
2008年から一部で試験的に取り入れていた生酛造りを、すべての酒に展開するには、大きな覚悟が必要となる。
しかも2021年は、藤井氏にとって経営面でも過去最大の試練に見舞われた年だった。
この年、2018年に続く二度目の水害が蔵を襲い、小さな用水路の氾濫で排水ポンプが故障。6時間以上も水が引かず、仕込み設備に深刻なダメージを負った。
さらに追い打ちをかけたのが、前年からのコロナ禍による観光需要の急減。出荷は落ち込み、イベントも中止。売上は大きく下がった。
しかし藤井氏は、その逆風のなかでこそ意思を固める。
「本当にやりたいことに向き合うなら、いましかない」
腹を括った藤井氏は、全量生酛仕込みへの完全移行を断行。さらにもう一歩進んだ挑戦――酵母を一切添加しない「酵母無添加生酛」へと踏み込んでいく。
 89種の蔵付き酵母が織り成す唯一無二
89種の蔵付き酵母が織り成す唯一無二
酵母無添加による初めての仕込みは、大きな試練となった。
「最初の酒母はまったく発酵しなかったんです。40日経っても、もろみのアルコール度数は5%にも満たなかった」
不安を抱えつつ、仕込んだもろみを県内の醸造支援機関へ送り、解析を依頼。
その結果、驚くべきことが判明する。蔵内には89種類もの酵母が棲みついていたのだ。
「多様すぎて、どれか一つが優勢になれなかったんでしょうね。だから発酵が進まなかった」
とはいえ、酵母の密度は十分だったようで、そのまま主発酵へと進めると、酒として無事に完成。味わいは乳酸とリンゴ酸が重なり合う、酸味の立ったフルーティな酒だったという。
あまりに実験的だったため、「龍勢」の名は冠さなかったが、この経験は、藤井氏の考えに一つの確信をもたらす。
「環境さえ整えれば、うちの蔵付き酵母たちは自分たちで育ってくれる」
酵母を“選ぶ”のではなく“整える”。
その哲学が、今日における藤井酒造の酒造りの礎となっている。
 「日本酒アッサンブラージュ」で広がる可能性
「日本酒アッサンブラージュ」で広がる可能性
そのテーマは「アッサンブラージュ(ブレンド)」。異なる造りの日本酒をブレンドし、一つの調和へと導く発想だ。オリジナル日本酒づくり体験施設『My Sake World』では、[龍勢 黒ラベル 純米大吟醸]がブレンドに使用する日本酒に選ばれている。

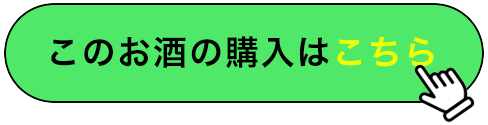
関連記事はこちら

- 京都の新体験施設!オリジナルの日本酒づくり【My Sake World 御池別邸】
-
♯MySakeWorld
関連記事はこちら

- 自分だけの日本酒づくり体験ができる【My Sake World 京都河原町店】当日受付可能、新感覚SAKE体験!
-
♯MySakeWorld
季節限定商品「番外品」は、精米歩合も酒米の銘柄も明記せず、蔵で生まれた多様な酒をブレンド。毎年異なる味わいでリリースされるロングセラー商品だ。「『混ぜると面白いよね』、というマインドは、酒蔵ならみんな少なからず持っていると思うんです」Sake Worldとの協業は、酒蔵が本来持つ感覚を社会へ新しい形で開く実験でもある。ブレンドによって生まれる味わいそのものが物語を語る――そんな日本酒を、体験として世界に届ける。
それは藤井氏が掲げる「伝えるための酒」とも重なる。
 空白の80年と100年後の未来へ
空白の80年と100年後の未来へ
1907年に日本一の栄誉に輝いた「龍勢」。当時の出品酒は、雄町を使い、蔵付き酵母で、伝統的な生酛造りだった。その後、戦後80年近くにわたって誰もその味わいと伝統を再現することなく時が流れた。
「僕の役割は、その空白の80年を埋める基盤を築くことだと思っています。もし、『龍勢』があのまま続いていたら、今どういう酒になっていたか。その架空の歴史を現実にすることが、自分の使命です。」

藤井氏は、事業の永続性について独自の哲学を持つ。
「永続性には2種類あると思っていて、ひとつは儲かるビジネスとしての永続。もうひとつは、文化を守り伝えていく永続。どちらも大事ですが、うちはどちらかといえば後者でありたい」
伝統の本質を現代的に再定義していくことで「龍勢」は、次の100年を生きる準備を始めている。
ライター:
山口吾往子
1995年京都大学法学部卒。2010年2月英語通訳案内士合格。日本酒好きが高じて、唎酒師と国際唎酒師、FBO認定日本酒学講師資格を取得。The Sake Educational Councilの認定資格、Certified Advanced Sake Professional (ASP)取得。2017年より日本語・英語双方のメディアで記事を執筆、日本酒の内外での動きについて伝える。また、2019年5月よりWSET sake Educatorとして大阪心斎橋にてWSET日本酒講座を行っている。

藤井酒造株式会社
- 創業
- 1863年(文久3年)
- 代表銘柄
- 龍勢・夜の帝王・宝寿
- 住所
- 広島県竹原市本町3-4-14Googlemapで開く
- TEL
- 0846-22-2029
- 営業時間
- 8:30~12:00、13:00~17:00
- 定休日
- 土曜日、日曜日








 海外から見出した「使命」
海外から見出した「使命」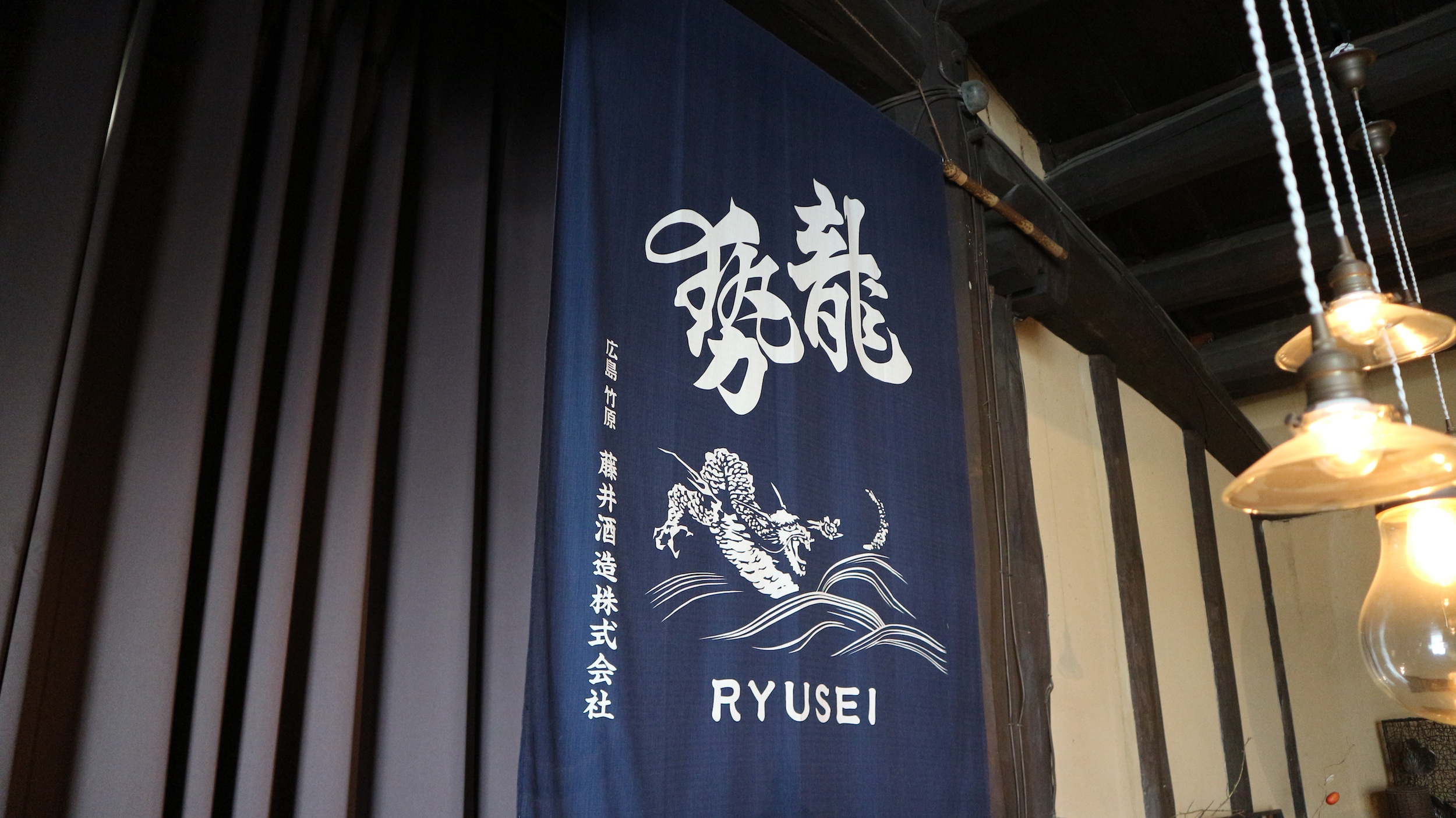 龍勢、隆盛と再起
龍勢、隆盛と再起 全量生酛仕込みへ――水害とコロナ禍の逆境で下した決断
全量生酛仕込みへ――水害とコロナ禍の逆境で下した決断 89種の蔵付き酵母が織り成す唯一無二
89種の蔵付き酵母が織り成す唯一無二 「日本酒アッサンブラージュ」で広がる可能性
「日本酒アッサンブラージュ」で広がる可能性 空白の80年と100年後の未来へ
空白の80年と100年後の未来へ




















![[鳥せい本店]が2026年で創業50周年!酒蔵直営ならではの取り組みに迫る。](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/3B9A3743-600x400.jpg)













