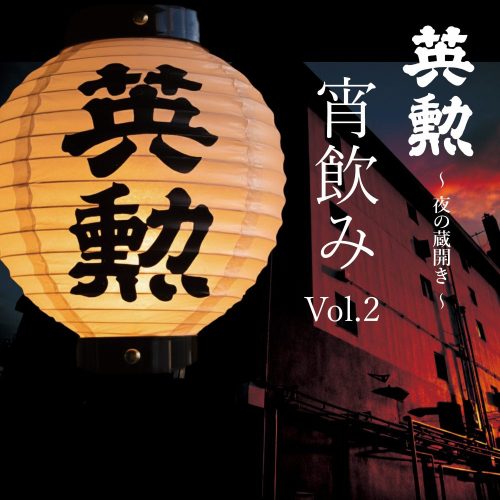ブレンドは[剣菱]の生命線。江戸時代から変わらぬ味を守り抜く。
[剣菱酒造] 4代目蔵元 白樫政孝さんインタビュー
歌川広重の浮世絵『東海道五十三次』に登場し、赤穂浪士が討ち入り前の出陣酒として飲んだといわれる剣菱。約500年の歴史があり、灘五郷で最も古い酒蔵として知られる。江戸時代から受け継がれる銘酒の味に、重要な役割を果たすのがブレンドの技。その極意に迫ってみた。

古くは江戸の町で下り酒として愛された銘酒・剣菱。広く人々に愛されたその味は、ブレンドによって生み出されたものだ。今も受け継がれているブレンドの理由やその手法について、4代目蔵元の白樫政孝さんにインタビューした。
この方に話を聞きました

- 剣菱酒造株式会社 代表取締役社長 白樫政孝さん
-
プロフィール1977年生まれ、兵庫県出身。甲南大学経営学部を卒業後、1990年に剣菱酒造入社。2017年より代表取締役に就任、4代目蔵元となる。農林水産省登録農産物検査員。
江戸時代から守り続ける剣菱の味

剣菱酒造の代表銘柄 剣菱 辛みと旨みのバランスに優れたやわらかな口当たりは、燗酒にするとより旨みが引き立つ。 黒松剣菱 米の濃醇な味わい。旨みと酸味、辛みが調和したコクとキレの良さ。 極上黒松剣菱 力強い旨み、甘みと辛みが絶妙に調和する飲み応えは抜群。“極上”の一献。
永生2(1505)年、伊丹で創業。昭和4(1929)年に酒蔵を灘へ移し、合わせて500年以上の歴史がある。剣菱酒造では大事な家訓が3つある、「止まった時計でいろ」「お客さまからいただいた資金は、お客さまのお口にお返ししよう」「一般のお客様が少し背伸びしたら手の届く価格までにしろ」。
特に一つ目には、流行を追わずに信念を持って味を守れという意味が込められており、熟成させた原酒をブレンドする手法はそのままに、江戸時代から変わらぬ“剣菱の味”を貫き続けている。浜蔵、中蔵、魚崎蔵の3つの醸造所を構える規模の大きさにもかかわらず、要となる麹作りはすべて蔵人による手仕事。また、米を蒸す甑や暖気樽など木製の酒造道具、菰樽用のわら縄を製作する自社工房を設け、伝統技術の継承にも尽力している。
ブレンドでどんな料理にも合う複雑な味わいに

—剣菱酒造のお酒にとって、ブレンドはどういう意味があるのでしょうか?
白樫さん「ブレンドは剣菱の生命線です。要は江戸の町で酒を売るためだったんですね。江戸時代に遡れば、当時われわれの酒は地酒ではなく“下り酒”だったわけです(※江戸時代、池田や伊丹、灘の上質な酒は江戸の町に舟で運ばれ、下り酒としてもてはやされた)。地酒であれば地元の料理に合わせて作ればいいが、江戸の町ではどんな料理に合わせられるかわからない。ならば酒の味を複雑にするほど合う料理も増えるだろう。複雑にするにはブレンドをすればいいという理屈です。酒の安定性と複雑性、ペアリングの幅を広げるという3つの手段が一気にできるというので始まったのでしょう。現代において料理は変わりましたが、人間の味覚は変わらない。理論は同じなので今でも通用するだろうというのがうちの考えです。」
—江戸時代から変わらない剣菱の味は、ブレンドによって守られているということですね。
白樫さん「現在は一人のブレンダーと4〜5人のチェッカーがおります。分析検査に頼ると数字ばかりを見てしまうので、人間の官能が一番ですね。味覚についてはブレンダーもチェッカーもそれぞれ感じ方のクセと特徴がありますので、複数人で修正しながら決めるわけです。少ないもので4本、多いものは10数本のタンクからブレンドをしています。」
—ブレンドをする上での完成形というのは意識されているのですか?
白樫さん「完成形をどう作るか、滅多に新しい商品を作らないのでイメージ、概念の話になるんですが、完璧からちょっとだけずらす。その方がとっかかりがいいんですよね。完璧な味にすると、なんか料理と積み上がっていかない、ちょっとだけの違和感を残したい。積み木を重ねるよりも、レゴブロックのようにちょっとした“ポツ”があった方が安定するのと同じ感じでしょうか。」
お酒は遊び道具、自由に飲んでいい

—弊社が運営している[My Sake World]という日本酒のブレンドに着目した事業については、どのようなご感想をお持ちですか?
白樫さん「すごくおもしろいなと思いました。やっぱりお客様がその場で楽しめる、体感できるというのは大切です。われわれ日本酒業界が今までできなかったことで、それによってファンも増えるし、日本酒についての理解も深まる。うちがやりたかったな(笑)。」
—一般のお客様からは「日本酒をブレンドしてもいいの?」とよく言われるのですが、ブレンドは江戸時代からある技術ということをお伝えしています。[My Sake World]では、蔵を越えて酒をブレンドすることで日本酒の新しい価値を生み出すことを目指しています。
白樫さん「江戸時代の小売店は、ずっとそれと同じことをやってきたわけです(※異なる酒蔵同士のブレンド)。ブレンドによる自分の店の味がウリだった。そういう意味では、お酒の楽しみが縮こまっていたのを広げてもらったと感じています。うちでも2019年に [竹泉]さんとのブレンドを発売したことがありますよ。1年経ったら馴染むかと思ったけれど、味が落ち着くのに5年かかりました。やっぱり育ちが違うもん同士、合うのは時間がかかった。基本的にお酒は遊び道具ですので、僕らの手を離れたら自由にしてもらっていい。例えば何かで割るとか、水を足すとか、好きな温度で飲むとか。江戸時代には十返舎一九が日本酒をいろいろ割って飲んだレシピが残っているくらいです。だから伝統を崩しているなんてことはまったくない、どんどん遊んでもらいたい。」
関連記事はこちら

- 自分だけの日本酒づくり体験ができる【My Sake World 京都河原町店】当日受付可能、新感覚SAKE体験!
-
♯MySakeWorld
代々伝えられてきた熟成のための技

—剣菱さんのお酒は何年か落ち着かせて、熟成してから提供されているとか。
白樫さん「昔はみんな熟成酒だったからという理由です。うちでは熟成をさせるためにこういう酒質を作れという基準があるのですが、それがことごとく今の教科書とは正反対。麹の温度からもろみの温度、仕込みに配合まで、全部枠から外れてる。入社して最初の半年、醸造試験場に行く時に『いいですか、習ったことは全部違うと思って帰ってきてください』って技師に言われたくらい。ほんと見事にうちの新酒はおいしくないんですが熟成中にちゃんとおいしくなっていく。その理由が会社に入ってからはいろんな情報が手に入るようになったので、ずっと口伝されてきたうちの技法にどういう意味があるかが科学的にわかってきた。これをマスキングするためにこの香りを出せって言ったんだとか、劣化より熟成を早く進めるためにここの数字にこだわってるんだとかが見えてきたんで、めちゃくちゃおもしろくなりました。ちゃんとうちの先祖はゴールから逆算してたんやなとわかりました。」
日本酒事業を通じて社会貢献ができれば

—今後、計画されていることはありますか?
白樫さん「太いわら縄を作る業者が廃業して、菰樽を巻くのにポリプロピレンの縄しかなくなってしまったんです。それって神社に奉納するのになんか嫌じゃないですか。で、ちょっとムカついたから、古い機械を買ってきてうちで作ることにしました。本当に感情的に嫌だったから始めたことなんですが、化学繊維は長く飾っていたらどうしてもボロボロになって、マイクロプラスチックをばら撒いてしまう。のちに聞いたら神事においてわら縄には邪気を吸うという意味があり、麻が払った邪気をわらが吸収する。それをとんど焼きで燃やすまでが神事だそうです。祇園祭でも鉾を立てる時はわら縄で縛って後で燃やすのは、邪気を吸っているから。じゃあ、わら縄は残す必要があるよねって。意味は後からついてきた感じです。」
—わら縄作りの工房まで設けられたとはすごいですね。
白樫さん「そんなんで今考えているのは、お客様にどう付加価値をお渡しできるかということ。美味しいお酒を提供するのは当たり前、それに加えて剣菱を飲めば飲むほど、日本の伝統的な技術の継承ができる、環境保護ができる、日本人の宗教的なアイデンティティを守っていける。そういうことに興味があるお客様はたくさんおられると思いますが、寄付もボランティアもしなくていい、宴会をしてくれたらいい(笑)。事業活動を通じての活性化です。SDGsは持続可能を目標にしていますが、われわれが目指すのはリジェネラティブ(再生・回復)。社会が良くなるための活動が、日本酒を飲むことによって進むというのが理想ですね。」

インタビューの後、今年度の作りが始まる直前の浜蔵を案内してもらった。息をのんだのは麹室にぎっしりと積み上げられた麹蓋の山。その数は約3000枚に上るのだとか。現代では麹作りの機械化が進み、伝統製法でも効率の良い大型の麹箱の使用が一般的。吟醸造りでは麹蓋を用いる場合があるが、容量が小さく小回りが効く分、何倍も手間がかかる。これだけの規模の酒蔵において、麹のすべてを人の手によって蓋麹作りで行っていることに驚かされた。お酒の味に関わらない部分は合理化し、守るべきところは頑なに守るという信念に感じいる。4代目の白樫さんは酒蔵を継ぐ決心をした理由について、「当時の流行の味ではない、他人に経営を任せると酒の味が変わる可能性がある。自分が責任を負うことが剣菱の味を守るために有効と思った」と語ってくれた。江戸の町人たちが酔いしれた変わらない旨さ。どんな料理にも合う剣菱の味は、これからの100 年先も受け継がれていくに違いない。
ライター・唎酒師 藤田えり子
大阪の日本酒専門店に世界を広げていただき、さまざまな日本酒や酒蔵に出合う。好きな日本酒は秋鹿、王祿ほか
お酒以外の趣味は鉱物集めとアゲハ蝶飼育。
剣菱酒造株式会社
- 創業
- 永生2(1505)年
- 代表銘柄
- 剣菱
- 住所
- 神戸市東灘区御影本町3-12-5(本社)
- TEL
- 078-451-2501

























![店では出せないワクワクと楽しみがある場所My Sake World体験レビュー[Mr SAKE2024準グランプリ 島田昇忠さん]](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/noritada_shimada-500x500.jpg)
![[徳島/本家松浦酒造場]酒蔵を中心に地域活性化につなげる「酒蔵体験プログラム」を取材](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/main_narutotai-500x500.jpg)




![酒を起点に人が渦巻く街広島・竹原[前川酒店]と[道の駅たけはら]を探訪](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/11/1-600x337.jpg)