日本の未来を照らすものが『國酒』大分・泰侍インタビュー(前編)
日本酒は日本を代表する「國酒」であると同時に、日本文化の歴史を照らす重要な「アイコン」のひとつだ。そんな文化的価値を伝えることを目的に、酒ビジネスを展開しているのが大分県にある泰侍(たいし)株式会社。主に海外に向けて伝承を行う同社を、同じく九州にルーツを持つ「旅するソムリエ」岸原文顕氏が訪れた。
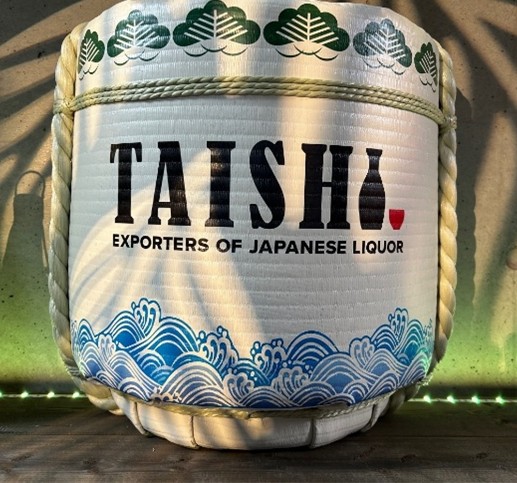
泰侍株式会社は、国産の酒類を世界へ輸出するサポートに加え、日本の文化的価値を伝えるため、海外での教育活動や酒類専門映像の制作、国内コミュニティの運営などを事業としている。
今回の訪問では、代表を務める幸松香乙里氏と、長年にわたりタッグを組むセールス&マーケティングマネージャー伊藤ノリ氏が迎えてくれた。
終始和やかな雰囲気で進んだインタビューでは、世界文化遺産にも位置づけられるようになった「國酒」への想いあふれる熱がこもった内容となった。

撮影スタジオがある泰侍株式会社オフィス(登記本社は別場所に所在)
カナダから始まった二人三脚
岸原:
創業のきっかけと、お二人の出会いについて教えてください。
幸松:
子供服を扱う商社に勤めたあとで、23歳から香港で暮らしてキャセイパシフィック航空のキャビンアテンダントをしていました。
そのうち出身地の大分の蔵元をサポートしたいと思うようになり現在に至ります。元々お酒はあまり詳しくなかったのですが、シンガポールで、初めて現地向けに日本酒を紹介した専門家に教わりました。
彼と連絡を取り、2年間で約200軒の飲食店を一緒に回ったのが創業の原点です。全国の蔵元を訪ね、現場を見せていただきながら経験を積みました。その後、JETROとの協働で、地元大分の6つの焼酎蔵の商品を香港で展示しました。
伊藤:
2021年までカナダで暮らしていて主にトロントを拠点にしていましたが、2014年から2017年の間はオンタリオ州の酒造会社でセールスとマーケティングに携わりました。
カナダに行く以前はAppleで働いていましたが、Appleは商品のスペックや機能を伝えるのではなく、生活をどう魅力的に変えてくれるのかという「ストーリー」を語っていました。
お酒も同じで、当時売っていた「NAMASAKE(生酒)」を買ってくれたのは、商品の背景にあるストーリーに共感した人でした。スペックに対してお金を払っていると思われがちですが、実際はそうではなくストーリーがお客様にとって重要だということです。
カナダだけではなく、カリフォルニア(アメリカ)で販売されている日本酒も同様で、どこの蔵かという情報よりも、誰がどんな想いで造っているのか、杜氏はどんなこだわりを持っているかという背景が伝わることが価値になると確信しました。
そうしたなかで、私たちはカナダでの展示会の場で偶然出会いました。それぞれの日本酒に対する思いを語り合ううち意気投合し、今に至っています。

幸松香乙里社長(左)と伊藤ノリ氏(右) 自社撮影スタジオにて
誰がための酒造り
岸原:
泰侍のホームページでは、「職人の技」「地域の歴史」「一滴一滴の価値」という言葉がありますが、風土と歴史が酒造りに深く関わっていることを訴求していますね。
幸松:
私たちの事業は、蔵元さんが安全に輸出できる支援です。東日本大震災後の福島など、観光客が訪れない地域にも足を運び、現地の酒蔵と連携して進めてきました。
海外では福島のお酒は「いらない」と言う人もいれば、「素晴らしいお酒だ」と評価する人もいます。徐々に受け入れられるようになってきましたが、振り返れば長い道のりでしたね。
全国の蔵を回る中で、造り手から忘れられないような話を聞く機会も多くありました。
例えば、出雲板倉酒造の村藤さんからは、「神様に祈りながら酒を造っている」という話を伺いました。
マーケティングでは都会に住む30代女性をターゲットに…というようなことを言いますが、そうではなく、神に捧げるために造っている。だからこそ、造り手は一切の妥協をせず真剣に取り組むのだと感じたのです。
日本では神社とお酒がセットで考えられてきた歴史があり、その精神性は今も受け継がれています。
お米の尊さを理解し、それを最良の姿にし、捧げるために酒を造る。そのような思いが込められているからこそ、日本酒には深い価値があるのだと思います。
「焼酎」もうひとつの國酒
岸原:
焼酎にも注力されていますね。公式YouTubeチャンネル「Sip of Japan」では、カナダ人男性2人が焼酎を飲んで「日本酒とは違って面白い!」と言いながら楽しそうでした。
ただ、焼酎は食中酒としてのイメージがまだ定着していないため、飲み方の提案が難しいという課題があります。
幸松:
さらにいえば、焼酎は台湾やベトナム、韓国(Soju)でも造られており、日本だけのものではありません。そのため、原産地表示やライセンスの問題もあります。酒税やライセンス料も高額で、海外での販売には高いハードルがあります。
日本ではお手頃な価格で市民権を得ており、非常に売りやすいですが、海外では価格が高く、販売できる店舗も限られています。ワインやウイスキーのように、アルコール度数によって税制が変わるため、焼酎がその枠に入れるかどうかが課題です。
伊藤:
例えば、カナダではスーパーマーケットでワインやビールが買えるようになったのは最近のことで、それ以前はワインは専門店でしか購入できませんでした。日本酒を「ライスワイン」として扱うことで、ワインと同じ棚に並べる工夫もされていますが、実際にはスーパーでは並ばないのが現状です。
焼酎を購入するにも、ウイスキーと同様にLCBO(酒類販売公社)などの専門店に行く必要があり、販売場所も限られています。ボトル単価も高く、日本酒よりもさらに入手しづらい状況です。
アルコール度数が25度でも40度でも、海外ではあまり違いがないとされており、むしろ40度の方が好まれる傾向があります。しかし、アルコール度数に応じて酒税が高くなるので、よほど強い魅力や個性がない限り売れにくくなります。
幸松:
蕎麦焼酎などは原料のユニークさが評価されることもあり、実際にオランダ向けの輸出が伸びています。これまではチャンスがなかなか巡ってこなかったのですが、焼酎は今後海外で成長する可能性が大きく、日本酒と並んで注力すべき分野ですね。
日本酒はメジャーブランド中心に多くが海外に展開していますが、焼酎はまだ未進出の酒蔵が多くあります。長野の蕎麦焼酎など、良い焼酎があるにもかかわらず、その価値が十分に伝わっていないのが課題ですね。
売れ筋の焼酎はイオン交換によって分子構造を変え、すっきりとした味わいに仕上げるなど、技術的にも高度な加工が施されています。一方で、例えば大分の焼酎の「原型」はどんなものだったのかというと、フィルタリングをほとんどせず、麹づくりも手作業、蒸留器も木製という伝統的な造り方のものです。
このような焼酎は、感動を覚えるほどのおいしさです。新たな形で商品化することで、焼酎の可能性を広げたいという強い思いがあります。
水で薄めることなく、力強く、アロマや味の複雑さが詰まった焼酎は、これまでにない魅力を持っています。焼酎の概念を打ち破り、蒸留酒としての新たな価値を提示したいです。

スタジオには様々な九州の酒
「九州」日本が世界に誇る酒造り島
岸原:
私は通訳ガイドもしていて、先日はアメリカからお酒好きのゲストを福岡・熊本・鹿児島の3県を案内しました。
日本にはすでに7〜8回ほど来ている方々で、酒蔵へ訪れるほど、日本酒知識も豊富でしたが、九州は初めてで焼酎に大変興味をもっていました。蔵や店に行き、豊富な種類の焼酎を試す体験を楽しんでいました。
幸松:
九州という島は、本当に驚くべき場所です。仕事を始めた頃から、焼酎は世界一の蒸留酒だと感じてきました。
規制や度数の制限がある中でも、世界に向けて焼酎を発信できるだけの潜在力があります。九州全体が世界に誇れる蒸留酒産地です。
現在、焼酎の良さを伝える商品づくりを進めています。課題も多いですが、原型を見せることでその価値を伝えたいと考えています。来年で事業を始めて10年になりますが、これまで焼酎を輸出する機会は少なく、まずは「焼酎とはこんなに素晴らしいものなのだ」と伝えることから始めたいと思っています。
岸原:
具体的にはどのような商品なのでしょうか?
幸松:
小手川酒造さんとの取り組みで、全く新しいブランドを立ち上げようとしています。それは焼酎という概念を取り払ったような商品です。蔵元からは「水を少し加えてほしい」と言われましたが、「水を一滴も入れずに出させてください」とお願いしディスカッションを重ねました。
水を加えることでまろやかな味わいが広がるという意見もありますが、私は「原型」を出したいという思いが強く、大分の麦焼酎の良さを凝縮した商品に仕上げたいと考えています。まずは焼酎の原型を理解してもらい、その後に水を加えたものとの違いを体験してもらうことで、“衝撃”をお届けしたいですね。
焼酎の「原型」と「熟成」
ここで年代別での焼酎試飲タイムに入った。
幸松&伊藤:
焼酎は時間の経過による味の変化を楽しめる蒸留酒です。3つの異なる年代ごとで、味の違いを体験してみませんか?
こちらはホーロータンクでの熟成をさせた商品です。ホーロータンクの中では色が全くつかないため、見た目だけでは熟成度合いが分かりません。熟成によって色がついた商品がありますが、それは樽の木や甕などの影響によるものであり、必ずしも品質の指標ではありません。

左から、2006年、1992年、1987年の3つの年代が異なる原酒のサンプル
岸原:
それぞれ個性的で香りもまったく異なり、芋のような香りやリンゴのような爽やかなタイプ、さらには柑橘系まで感じられ不思議ですね。真ん中(1992年)が一番好きですが、これは力強さとバランスが両立していて枯れた葉の香りがふわっと広がる感覚があり、非常に印象的です。
幸松:
この焼酎は米麹ではなく麦麹を使用しており、その年の麦がどんな味わいを生み出すかという、非常に純粋な造りです。麦からフローラルな香りやラズベリーの香りが生まれるなど、年代によって香りが変化するのも魅力です。焼酎の天井を打ち破りたいという強い意志があります。30年以上前のものですが、まるで「地球の絞り汁」のようです。
岸原:
大分の麦焼酎はすっきりとしたタイプが多く、洗練されていて食事にもよく合います。ただ、過去の焼酎ブームの際に「すっきりしているので飲みやすい」とステレオタイプで語られたのは、もったいないと思っていました。これらのサンプルは複雑な味わいが凝縮されていて、まさに“スピリッツ”と呼ぶにふさわしい存在ですね。とろみがあり柔らかく、アロマが弾けるような印象で面白い体験です。
幸松:
焼酎には本来これほどの力強さがあるのに、それが十分に伝わっていないのは残念です。
蔵元によっては、濃い焼酎を樽に入れたまま熟成させているものもあり、それがまた非常に美味しいのです。海外のバイヤーが蔵を訪れ、「会社ごと買いたい」と言うほどの反響をいただくこともあります。
岸原:
ウイスキーは樽熟成の神秘性が語られますが、麹による複雑さはまたひとつ異なる魅力があります。また、熟成の楽しみ方も違い、木樽や甕(かめ)を使った熟成ではなくホーロータンクの中で原酒だけで熟成させるという点は面白いですね。
幸松:
この焼酎は720mlで数万円の想定価格ですが、30年以上熟成された価値を考えれば、十分に納得できる価格です。志とストーリーが共感されれば、価格は後からついてくるものだと思います。
伊藤:
価格が高くても、熱心なファンが支えてくれるビジネスモデルが成立すれば、量を多く造って利益を得るよりも、少量でも価値を高めて利益を得る方が良いと感じます。
幸松:
木製蒸留器のメンテナンスにも予算が必要であり、良いものを造り続けるためには財力も必要です。こだわりがあるならば、それに見合った価格設定が必要です。
ただ、造り手が自身の商品の価値を言葉にすることは難しく、翻訳して伝える役割が必要です。ノリさんがされている仕事は、まさにその橋渡しであり、物語として言葉で伝え、飲んで体感してもらうことが重要です。
岸原:
蒸気で蒸留していることを知らない人も多く、実際の様子を映像で見せることで、「なるほど」と思ってもらえるはずですね。良い映像があると、より飲みたくなって嗜好品としての魅力が高まります。映画は、映像・音楽・役者・セリフが融合する“総合芸術”ですが、お酒も同じですね。
伊藤:
泰侍の事業をする中で、商品の品質だけでなく、写真や映像、ホームページなどの表現も重要になります。かおりさんのお父様が写真を長年撮られていたこともあり、ここは制作環境が整っています。
さらに海外の人に見てもらうためには、良いウェブサイトも必要です。英語対応も含めて、酒蔵やお酒の価値発信のためそうしたサポートをどんどん進めていきます。
________________________________________
ここまでは焼酎を含めた「國酒」について語っていただいた。
カナダで出会い、世界への玄関口・九州を拠点とする泰侍は、目線も自然と外に向けられている。一方、日本酒・焼酎ともにそれぞれの酒蔵が持つ「ストーリー」を予め認識した上で、事業を展開していることも注目すべき点だ。また、公式オンラインショップではオリジナル酒もラインナップに加わるなど、酒に対する愛情はどこまでも深い。

泰侍オリジナル酒”KABOSHU & UMESHU” 。瑞々しく上質なあまみが特長。
そんな泰侍を率いる幸松さん・伊藤さんが、現在注力していることのひとつが「発信」という。後編では、その詳細について伺った。
ライター:
岸原文顕/ ソムリエ、HBAカクテルアドバイザー。日本酒をはじめ世界の酒類文化をこよなく愛する。世界3大ビールブランドや洋酒類のブランドマネジャーを歴任、
京都のクラフト醸造所経営など、国内外での酒類事業経験32年。日本発の志ある酒類の世界展開を支援。BOONE合同会社代表。全国通訳案内士。東京在住。
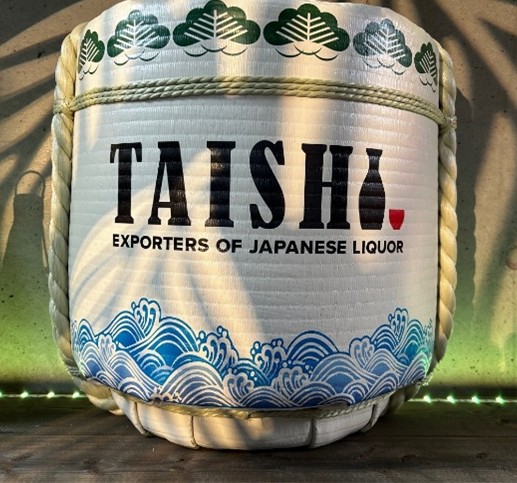

















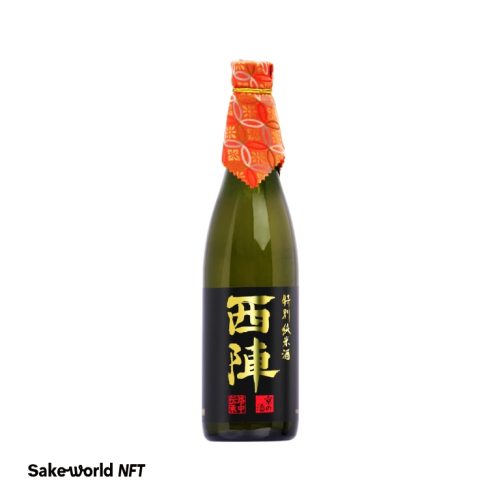




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















