【今さら聞けない教えて!?シリーズ17】火入れ 其の一 ~世界に先駆けた日本の低温加熱殺菌~
今回は、酵母や酵素の活動を止め、酒質の劣化を防ぎ、香味の安定を図り、長期保存を可能にするために行う “ 火入れ ” と呼ばれる作業についてお話しします。

パスツールの “低温殺菌法” 発表に先立つこと298年、日本では既に、酒を貯蔵前に加熱殺菌し、酵素の働きを止めて香味の熟成をはかる『火入れ』が行われていたという記録が残っています。
今回は、酵母や酵素の活動を止め、酒質の劣化を防ぎ、香味の安定を図り、長期保存を可能にするために行う “ 火入れ ” と呼ばれる作業についてお話しいたしましょう。
前回:【今さら聞けない教えて!?シリーズ16】滓引きと濾過~清らかに澄み渡れ!
この方が解説します

- 杜氏屋主人・プロデューサー中野恵利さん
-
プロフィール1995年、大阪・天神橋筋に日本酒バー「Janapese Refined Sake Bar 杜氏屋」を開店。日本酒評論家、セミナー講師、作詞家としてさまざまな分野で活躍。
● 多聞院日記 ~歴史の一級資料が物語る火入れ~
奈良県にある興福寺の塔頭・多聞院において、1478年(文明10)から1618年(元和4)にかけて三代の僧によって書き継がれた日記として知られている多聞院日記。
室町時代後期から江戸時代初頭までの畿内の情勢や寺院の儀式、物品購入を、私情をはさまず出来事だけを記述していることから、歴史の一級資料とされています。この、140年に渡る記録の中に、断片的に酒造にまつわる記述があるので、以下に抜粋いたします。
△ 第一度 酒ニサセ樽へ入了 永禄十一年六月二十三日 条
△ 酒ニサセ了、初度 永禄十二年五月二十日 条
△ 酒煮之 初度七斗程在之、一向不勝 元亀元年五月二十二日 条
△ 酒ヲニサセ了、初度也 元亀二年六月十六日 条
△ 酒ヲニサセ了 天正二年五月十三日 条
上記は、1568年から1574年にかけて見受けられる記述です。
“ 初度 ” “ 第一度 ” という言葉から、火入れは2回以上行われていたことが窺い知れます。
“ 酒ニサセ樽へ入了 ” からは、加熱後すぐに樽詰めする、後に “ 煮込 ” と呼ばれる作業が行われていたことが想像できます。
仮に、永禄11年(1568)を日本の火入れの成立としても、フランスのルイ パスツールが低温殺菌法を発表したのは1866年ですので、298年も先立っていたことは明らかです。
ただ、多聞院日記の記述から、加熱温度や時間について知ることは出来ません。
● 御酒之日記 ~ 記された酒造りの秘伝
多聞院日記と並び、資料価値の高い文書として注目されるものが『御酒之日記』です。
常陸国 佐竹家に伝わる古文書の一部『御酒之日記』には、“ あまの( 天野酒・天野山金剛寺で造られていた僧坊酒 )”“ 菩提泉( 菩提山正暦寺で造られていた僧坊酒 )” “ ねりぬき(博多産の絹練(練酒) ) ” といった文字が躍り、当時主に造られていた酒の製造法が記されています。
記述のなかには、後の時代の酒造文献にも登場する “ のみかん(飲み燗)” という言葉が認められ、これは40度くらいの火入れを差します。また、 “ てひきかん(手引き燗)”は、熱いっ! と手を引っ込める程度の温度と考察されます。さらに、“うへににるときあわたつは、泡ヲ能々可取”は、煮るときに上に泡が立ったらよく取れという指示で、これは、酒に含まれるタンパク質が熱変性を起こす50~60度程度の温度と考えられます。
『御酒之日記』は、東大資料編纂所所蔵の色川本写本の纂写年が永禄9年 (1566) であることから、原本の成立はそれ以前であることが安易に想像でき、『多聞院日記』に記された永禄11年(1568)より前から火入れは行われていたことになります。
● 酒造りの教科書
明確な年月日を知ることが出来る『多聞院日記』、低温での火入れの手順が示された『御酒之日記』、いずれも酒造りの歴史を垣間見ることが出来る一級資料であることは間違いありません。
そこから時代はさらに進み、江戸元禄期以降、『童蒙酒造記』『寒造酒屋永代記伝』といった、酒造りの様々な現象に関する詳細が合理的な方法とともに記載されている、酒造りの教科書的な酒造技術書が世に出るのですが、それについてはまた、そのうちお話いたしましょう。
前回:【今さら聞けない教えて!?シリーズ16】滓引きと濾過~清らかに澄み渡れ!


















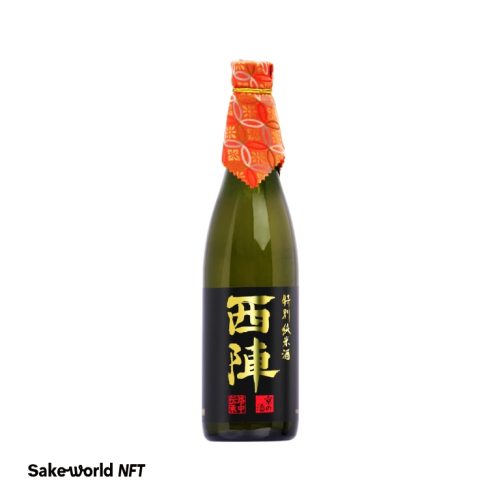




![[WORLD KYOTO]×[Sake World]肩を並べて飲む! 日本酒と音楽の楽しき世界](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/top-500x500.jpg)
![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)



















