Mrs SAKE デュケット智美さんが語る「インバウンド×酒蔵ツーリズム」が持つ無限の可能性
新潟県を拠点に、日本酒の魅力を世界に発信しているデュケット智美さん。これまで様々なアプローチをしてきた中、新たな挑戦として取り組んでいるのが、酒蔵の立ち上げとそこでの酒造り、さらにツーリズムを融合させた拠点づくりだ。今回Sake Worldでは醸造所立ち上げまでの経緯や、インバウンド時代における地域と世界をつなぐ“酒蔵ツーリズム”の可能性を聞いた。

酒蔵のPR映像制作や、お酒の祭典「にいがた醸造サミット」のプロデュース、日本酒文化を通した国際交流プロジェクト「Niigata Sake Lovers(ニイガタサケラバーズ)」の運営など、日本酒の魅力を国内外に伝えるため、デュケット智美さんの活動範囲は多岐にわたる。2024年にはMrs SAKE初代グランプリにも選出された。
そんなデュケットさんの新たな試みが、酒蔵「雪と里山醸造所」の立ち上げ。深い雪と豊かな里山の自然に囲まれた新潟県・十日町市で、この冬から酒造りを始めるとともに酒蔵ツーリズムにも挑戦する。
この方に話を聞きました

- Niigata Sake Lovers代表・Founder デュケット智美さん
-
プロフィール新潟県新潟市出身。唎酒師、国際日本酒学講師、TESOL認定英語講師、WEST Level3、栄養士などの資格を持つ。2024年にMrs SAKE初代グランプリを受賞し、2025年に自身初の酒蔵「雪と里山醸造所」を設立した。(10月28日付で新潟県酒造組合に加入し、新潟県の酒蔵は全国最多の90蔵になった)
日本酒の勉強から酒蔵を持つまで
――元々は海外で働かれていたデュケットさんが、新潟で日本酒に関わる仕事を始めたのはどうしてですか?
デュケット智美さん(以下略)
「20代の前半はカナダで街を象徴する五つ星ホテルの某フランス高級ブランドの代理店で勤務するなかで『世界の有名ブランドであっても自分の“好き”な商品から売れる』ことに気づき、情熱の大切さを学びました。20代後半はオランダ、イギリス、中国などでグリーンエネルギーの会社で翻訳通訳を含むマネジメントの仕事をしました。その後30代で日本へ戻って仕事をどうするか考えたときに、自分が一番『好きなもの』で起業しようと思い、それが通訳時代におもてなしで欠かせなかった『新潟の日本酒文化』だったんです。

まず『にいがた酒の陣(※1)』で名刺を持って回り酒蔵の方と色々お話したり、新潟に住む外国人の友人たちと酒蔵見学へ行ったのですが、通訳しようにも英語は話せても、私自身が日本酒のことや用語を全然知らないなと気づいて。そこから、『本物の日本を知りたい』という外国人たちと一緒に、日本酒について勉強するようになりました。そうするうちに、ある酒蔵さんから『そんなに頑張って勉強しているなら、酒造りも実際にやってみたら?』とお声がけいただいたんです」
(※1)にいがた酒の陣:年に1回、新潟県で開催される日本最大級の日本酒の祭典。
――勉強が酒造り体験にまで発展したんですね。
「そうなんです。そして2013年に、春に田植え、秋に稲刈り、冬に酒造りと、年間を通して仲間たちと一緒に米作りから(日本酒)製品化まで行うプロジェクト『Niigata Sake Lovers』を始めました。

Niigata Sake Loversの活動風景
『Niigata Sake Lovers』では、毎年違う酒蔵と組んで、それぞれの造り方を体験しながら活動を続けていたのですが、2020年のコロナ禍によって、酒蔵に外部の人が入ることがリスクになってしまったんです。
それでもこのプロジェクトは続けたいーそう思ったときに、『自分たちの酒蔵があればいいんじゃないか』と。それで、これまでの活動を昇華させた形で、酒蔵『雪と里山醸造所』を立ち上げることになりました。
新潟には美味しいお酒がたくさんありますが、一部を除いて知られていないという課題があります。まずはここで酒造りの面白さや楽しさを知ってもらうことで、ほかの酒蔵にも関心が広がるきっかけになればと考えています」
2つの顔を持つ「雪と里山醸造所」
――「雪と里山醸造所」立ち上げの背景には、様々な人に酒造りの工程を体験してもらうという目的があったんですね。
「ただ、酒造免許を持つ以上は、自分たちのプロダクトとして良いものを造りたいという想いもあったので、建物の2階部分を体験用にし、1階は酒蔵としてのお酒を造る用に分けました。
1階では30年以上の酒造り経験を持つメンバーを中心に、国内・海外それぞれ異なる酒造りをこの冬より始める予定です。
持続性も大切にしたいので、お米は自分たちで育てた無農薬・無化学肥料のものと、不足する分は十日町の信頼できる農家さんの無農薬・減農薬のお米を使い、電力は100%再生エネルギーにしようと計画しています」

――2階ではどういった「体験」を考えていますか?
「以前カナダに住んでいたときに、ワイナリーでマイワインを造らせてもらう経験をしたのですが、それがとても良かったんです。その経験をベースに、参加者が麹の種類や量、酵母の種類、甘口・辛口のバランスなどを自ら選んで、マイ日本酒を造れるような形にしようと思っています。
将来的には、地元の農家さんが自分で育てたお米を持ち込んで、そこからお酒に変えるようなこともできたらいいですね」
――それは素敵です!自分のお米がこんなに美味しいお酒になるんだ、と実感できると嬉しいですね。
「可能性しかない」インバウンド×酒蔵ツーリズム
――「雪と里山醸造所」では地元の方、日本人観光客に加えて海外からのお客さんも見込まれているかと思います。海外生活が長く、「Niigata Sake Lovers」でも、海外の方と関わることが多かったデュケットさんから見て、インバウンド目線の酒蔵ツーリズムの可能性についてはどうお考えですか?
「海外は本当に可能性しかないです。
昨年、Mrs SAKEの活動を通して海外の様々な地域に足を運んだときに、日本酒に興味を持つ方がとても増えていることを実感しました。年末には『伝統的酒造り』がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、これからもっと注目度は上がると思います。

フランスのイベントでは予想以上の来客で、会場へ入場規制がかかるほどの長蛇の列ができた。

香港「和酒アワード」のステージトークに香港のワインソムリエやスペシャリストと共に登壇。日本酒とチーズの相性についてのトークは大いに盛り上がった。
さらにコロナ禍以降、インバウンドのニーズが、爆買いに代表される“モノ”の消費から自分の国ではできない“体験”の消費にシフトしています。観光庁の調べによると、『もし日本滞在中に酒蔵ツアーがあることを知った場合、参加してみたいですか?』という質問に92%もの人が『はい』と答えたそうです。酒蔵の見学や試飲はもちろんですが、日本酒の造り方や歴史を学び、蔵人と交流することにも興味を持っている方が増えています。
ただ、それを実施できる酒蔵はまだ少ない。『雪と里山醸造所』は、世界中から人が集まって本物のお酒造りや日本酒の文化、歴史を学べる場所にしたいですね」
酒造業以外の業界も一緒になって盛り上げたい
――ところで明日(10月1日)、デュケットさんが設立理事として参画する「新潟酒蔵ツーリズム推進協議会」が発足しますね。
「この協議会は酒蔵ではなく観光業者が中心になって立ち上がったので、日本酒文化を観光とどう紐づけるか、という点で新しい道が見えるのではないかと考えています。

これまで、私みたいに観光のために酒蔵を立ち上げる人ってなかなかいなくて、元々酒造りをやっているなかで『ちょっと見せてもいいよ』という形での観光が入っていました。
でもそれって畑違いの仕事。だから酒蔵の方にとっては、負担が大きかったと思うんです。
今回はそこに、ホテル、タクシー、旅行会社といった観光のプロが入って『うちの地域にはこんな酒蔵があるんです!』と観光客との接点になってもらうことで、酒蔵の方はお酒造りに集中できます。酒造業以外の業界も一緒になって、酒蔵を観光のコンテンツのひとつとして県全体で盛り上げていきたいですね」
――そのなかで、デュケットさんが果たしたい役割はありますか?
「私は強みが食と海外なので、どういったお料理と日本酒が合うかの提案なども含めた、外国人に刺さるコンテンツ作りやPRですね。
『雪と里山醸造所』では、『Hotel醸す森』や『酒の宿 玉城屋』『ひなの宿 ちとせ』『ryugon』『里山十帖』など近隣の一流の宿泊施設と提携して、マリアージュや温泉、宿泊といった、この土地ならではの体験を日本酒文化と一緒に発信していきたいと思います。

あとは、こうした体験をガイドできる人が少ないので教育事業もやりたいです。英語はできるけれど日本酒文化について話せない人が多いので、そういった方に英語でどうガイドしたらいいかを教えていきたいです。
これは『Niigata Sake Lovers』としての活動のなかで気づいたことなんですが、日本酒の面白さを知ると、皆さんが勝手にアンバサダーとして日本酒をPRしてくれるようになるんです(笑)
だから、そういう人たちをもっと増やしていきたい。育成というより増殖のようなイメージですね」
自分にとって日本酒とは、「飲める文化」
――日本酒には、思わず広めたくなる魅力があります。最後に、デュケットさんにとって日本酒とは、どんな存在ですか?
「いっぱいありすぎて……一言でとなると『飲める文化』でしょうか。
そもそも日本酒は神様に捧げるための祈りのお酒。そして、結婚式や新年などお祝いでの乾杯や誰かが亡くなったときの献杯など、良いときも悪いときも日本人に寄り添ってくれたのが日本酒ですよね。人と人をつないでくれるものであり、海外に伝えたい誇りのひとつだと思います。
いま、棚田で米を育てていて脱穀も昔ながらの足踏み式の機械も使ってやっているんです。
こういうのを経験すると、農耕民族としての日本人の知恵が全部詰まっているから日本酒って言われるんだなって、よく分かります。
こうした積み重ねを知れば知るほど、日本酒のことを大切に思いますし、次の世代につなげていきたい気持ちが強くなっています」

自身初の醸造所を通して、酒蔵ツーリズムの新たな地平を切り開こうとしているデュケットさん。「海外には、可能性しかない」と語るきらきらした瞳には、国を超えて日本酒の素晴らしさを伝えていきたいという確かな意思が感じられた。
分野を横断してエネルギッシュに活動を続ける彼女の新しい挑戦が酒蔵ツーリズムにどんな風を吹き込むのか、楽しみに待ちたい。
(写真提供:デュケット智美さん)
ライター:卜部奏音
新潟県在住/酒匠・唎酒師・焼酎唎酒師
政府系機関で日本酒を含む食品の輸出支援に携わり、現在はフリーライターとして活動しています。甘味・酸味がはっきりしたタイプや副原料を使ったクラフトサケが好きです。https://www.foriio.com/k-urabe


















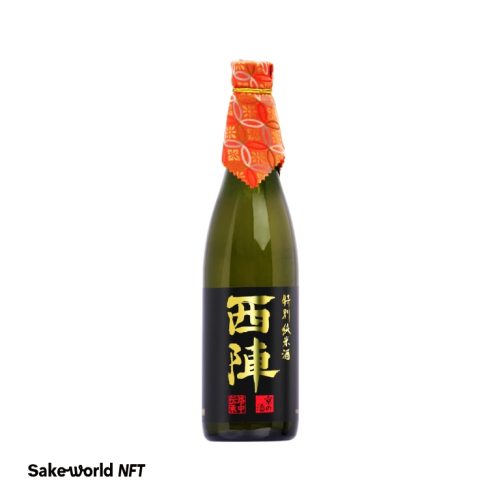




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















