酒蔵に宿泊できる
「蔵人体験」の先駆け!
[KURABITO STAY]が取り組む日本酒ツーリズムの考えを聞く!
酒蔵に宿泊しながら日本酒造りの工程を本格的に体験できる、そんなコンセプトで営業する長野県佐久市の酒蔵ホテル®が人気を集めている。[KURABITO STAY]代表の田澤麻里香さんが仕掛ける「蔵人体験」や日本酒ツーリズムの取り組みを聞いた。

みなさんは日本酒がどのようにできるかご存じだろうか。写真や映像で酒造りについて見た事がある方は多いとしても、それを実体験したことはあるだろうか。蒸米が炊き上がった時の香りや湯気、お酒の発酵を促す作業の「櫂入れ」の重さ、酵母の力により発酵タンクから聞こえる「ぷちぷちっ」と泡立つ音。そんな日本酒の姿を間近に見て体験できる酒蔵ホテル®[KURABITO STAY]を紹介しよう。
この方に話を聞きました

- 株式会社KURABITO STAY 代表 田澤麻里香さん
-
プロフィール長野県小諸市出身。青山学院大学卒業。大手旅行会社等に勤務後、故郷小諸市へUターン。地域の観光に関わるなかで発案した「酒蔵ホテル®」がビジネスコンテスト「みんなの夢AWARD」全国大会グランプリを受賞。2020年[KURABITO STAY]開業。昨年10月より内閣府クールジャパン・プロデューサーに就任。
KURABITO STAYとは
酒蔵ホテル®「KURABITO STAY」は、佐久市臼田にある創業元禄9年(1696年)の[橘倉酒蔵]の一角に令和2年(2020年)に開業。酒蔵での仕込みの他、麹造り、酒米の圃場を巡るサイクリングなど、その時期に応じた様々な体験が提供される。週末だけの営業スタイルながら現在までの宿泊者は700名を超え、海外29カ国の方がここを訪れている。

例をあげよう。日本酒の2泊3日の仕込み体験では酒蔵蔵人のサポートのもとに「洗米」「蒸し」「麹室への引き込み」の他、製造の時期によって「麹の選り分け」「検温」「酒母づくり(荒櫂)」「櫂入れ」などが体験メニューに組み入れられる。いろいろなプロセスで日本酒がどのように造られていくのかを間近に見て作業に関われるのは貴重な体験だ。

その他にも酒蔵が酒造りの最初に行う神主さんによる「お祓いの神事」や、作業の合間の蔵見学、日本酒のテイスティングセミナー、健康効果について詳しく解説する麹セミナーなども行われ、多彩で効率的なカリキュラムが組まれ飽きることなく時間を過ごすことになる。

秋から冬にかけての仕込み体験の他に、小学校高学年から参加できる1泊2日の麹造り体験や、昨年からは佐久地域の日本酒における「テロワール(風土)」ともいえる田園風景を巡るeバイクでのサイクリングのツアーも実施。通年での日本酒に関わる様々な体験ができるプログラムが揃うようになった。
KURABITO STAY誕生のきっかけ

――閑散期の酒蔵見学は世間で一般的なものだと思うのですが、酒蔵ホテル®とは奇抜なアイディアですね。キッカケはなんだったのでしょうか。
田澤さん―私が観光の仕事を立ち上げるためUターンで帰ってきたとき、故郷はとても寂れていました。また、仕事でお会いする方とお話ししても、夏は軽井沢が近いので観光の方の行き来がありますが、冬は寒く雪は降らないので誰も来ない状態。地元の方も「冬は、ここには何もない」と話されるのを聞いて残念に感じたのを覚えています。
では、改めて冬は何もないのかと周囲を見たときに、長野県佐久地域に13もある日本酒の酒蔵が寒造りの仕込みで稼働しているのを目にして、これが冬に人をこの地に呼び込むものになるのではないかと考えました。そこから、たまたま橘倉酒蔵の当時の井出平専務(現社長)の案内で蔵を見ているときに、敷地内で以前に酒の仕込みで杜氏や蔵人が泊まり込むのに使い、その時点では使われていなかった建物と出会ったのです。
ここに泊まってもらえれば、従来の酒蔵見学にはない日本酒体験が密度の濃いカリキュラムでお客様に満足いただけるのではないか。創業する人の根拠のない自信だったのかもしれませんが、それをビジネスプランとして発表し「みんなの夢AWARD」の全国大会グランプリを受賞したことで、実現に向けて動き出すこととなりました。
KURABITO STAY流の接客

――蔵人体験を泊まり込みでとなると相当な日本酒好きの方がいらっしゃるのですか。
田澤さん―日本酒が好きな方はもちろんですが、他にもいろいろな方がいらっしゃいます。例えば日本酒は飲めないけれど麹に興味があるのでお子様といっしょに参加されたとか、海外の方でワイナリーを持っていて日本酒も設備を備えて造れるものか体験に来たら造りの工程の繊細さに驚いたとか、興味の持たれ方は様々です。
1泊2日や2泊3日の限られた期間ですので、来られた方に高い満足感をお持ち帰りいただけるようカリキュラムを練っています。旅行代理店に勤務していた時に、短時間で多くの人が満足できるものを大量に数をこなしていくやり方に疑問を持ち、1時間滞在する100人の満足を追うのではなく100時間滞在する1人にしっかりと満足してもらいたいとの思いで宿泊された方への体験などの運営をしています。
昨年からはツーリズムを通して「佐久の日本酒を口に含んだ瞬間に、佐久の情景が思い浮かぶ」ことを目指し、サイクリングツアーも実施しています。
日本酒から見えた観光の可能性

――今年5月には長野県上田市の信州亀齢・岡崎酒造前に開業する酒蔵ホテル® KIREIの運営にも携わる田澤さんですが、これからの活動について教えてください。
田澤さん―私がやっていきたいのは地域の伝統産業を活かした「観光地域づくり」です。「ここには何もない」と謙遜している地方の方は多いと思いますが、それぞれの地域と文化に自信と誇りを取り戻せるような活動をしていきたいと考えています。
今はKURABITO STAYの代表ですが、もしかして佐久地域が豆腐の名産地だったら「豆腐ステイ」をやっていたのかもしれません(笑)。この地が日本酒の名醸地であったことで酒蔵ホテル®がスタートし、蔵人体験の方が街を歩かれることで自分たちの街が「人が訪れる場所」であると、地域の方の自信につながってきていると感じます。
ここでの経験によって単にお酒の消費が活発になることを期待するのではなく、日本酒について発信してくれる方がもっともっと多くなるといいと思っています。それが巡り巡って作り手と消費者だけの関係に留まらず、その周辺への興味・理解が深まります。その地のお酒、お酒を育む人、土地、文化が広く愛され、私たち関係者が目指している「100年後も誇れるふるさとを守り伝える」ことに繋がってほしい。そう願っています。
ライター Kunie
コロナ禍前まで長く東京で開催される各県酒造組合、「若手の夜明け」「酒縁川島」「千駄木稲毛屋」「荻窪いちべえ」や、御徒町や西荻窪の酒販店での日本酒会で舌を鍛えました。コロナを期に長野県に移住。時間を作って酒蔵の蔵人の真似事やワイナリーの援農、ブルワリーのタップルームや蒸留所巡りと、今もどっぷり浸かった「お酒の沼」から旬の情報をお伝えします。


















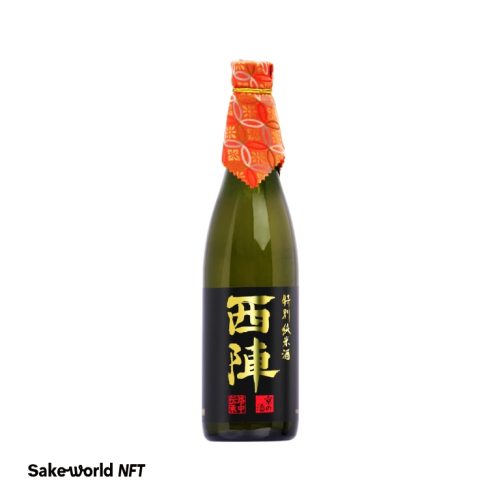




![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)





















